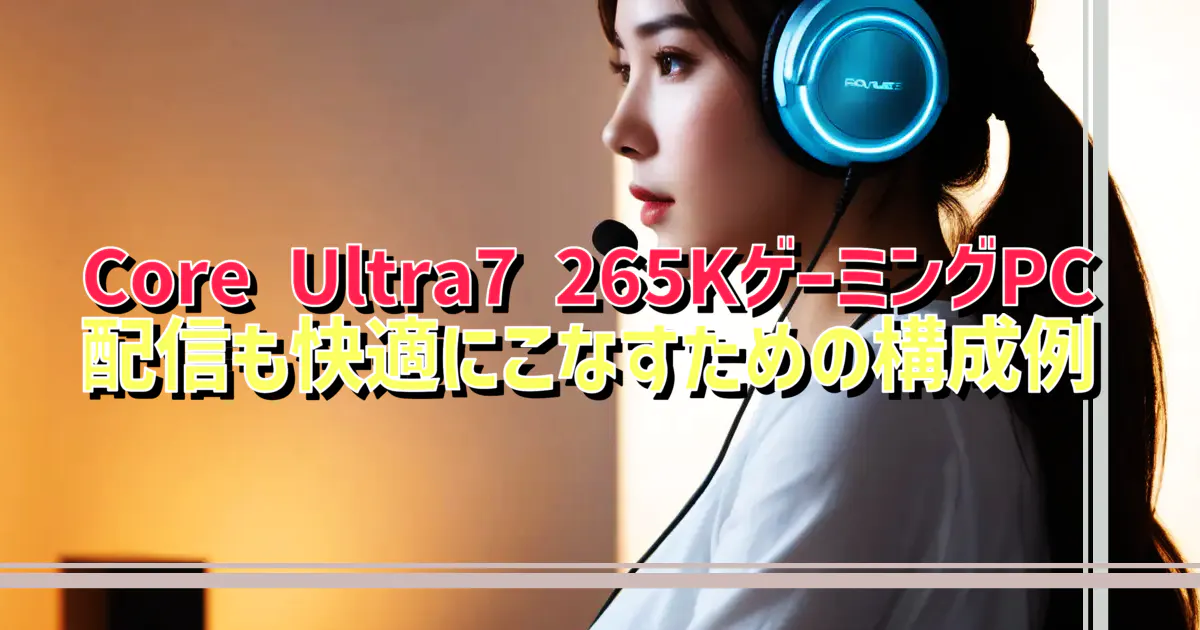Core Ultra7 265Kで組むゲーミングPC いま選ぶ理由とポイント

Core Ultra7 265Kの力を引き出すための実用的な工夫
スペック表や比較記事を見ていると数字だけに気を取られがちですが、実際に組んで長時間使ってみると「ここを甘く考えたせいで結局バランスが崩れたな」と思う場面に必ず出会うんです。
だから私は、冷却や電源、ケースやメモリなどを最初からきちんと考えることが一番大切だと心から思っています。
これは机上の話ではなく実際の体験で得た教訓です。
まず冷却の重要性ですが、このCPUは効率的になっているとはいえオーバークロック対応のKモデルである以上、やはり発熱は避けられません。
空冷ファンだけでも高品質なものを選べば何とか安定しますが、私は夜の配信を長時間続けることが多いので静音性も考慮し、結局は簡易水冷を導入しました。
ある晩のことですが、以前ならクロックダウンで映像がカクついてきた時間帯でも、水冷に変えてからは最後まで安定したクロックを維持したまま動いてくれたんです。
その瞬間に思わず「これは投資の価値があったぞ」と声に出てしまいました。
正直ホッとしましたよ。
それに加えてGPUとの相性もかなり大きな要素です。
どれだけ高性能なCPUでもGPUが弱ければ性能を発揮できず、宝の持ち腐れです。
私も過去に少し控えめなGPUをあえて組み合わせたことがあったのですが、その時はCPUが明らかに余力を残しているのにフレームレートが頭打ちとなり、納得できないもどかしい経験をしました。
今ならGeForce RTX5070Tiあたりが最もバランスが良いと感じています。
消費電力や価格のバランスも現実的で、ゲームも作業も両立可能。
もちろん予算に余裕があるなら上位モデルも悪くはないでしょうが、私は5070Tiで十分満足していて、「背伸びしすぎない賢い選択」だと思っています。
メモリも決して軽視できません。
最初に16GBで組んだ時は、ゲームだけなら問題なかったのですが、配信ソフトや動画編集アプリを同時に使うと一気に余裕がなくなりました。
そのため32GBに増設したものの、同時作業が多くなるとやはり不足感は残るんです。
最終的に64GBへと増やした際には、タスク切り替えが驚くほどスムーズになり「ああ、これが安心感か」と心から感じました。
もう以前には戻れませんね。
本当にそう思います。
ストレージも忘れてはいけない部分です。
導入したのはWD製のGen.4で、ロード速度が大幅に短縮。
以前は待ち時間にスマホをいじることもあったのですが、それができないほど一瞬でゲームが立ち上がるんです。
仲間と同じタイミングで起動しても私が必ず先にロビーへ入ってしまい、「また一番だな」と笑われるような場面も増えました。
その小さな優越感すら、このCPUの性能とストレージの組み合わせの成果です。
若い頃はどうしても見た目重視でガラス面積の多いものを選びがちでした。
しかしそれが災いして冷却効率が落ち、長時間の使用で不安定になるという失敗をしました。
そこでLian Liのケースを導入したところ、エアフローの設計が徹底されているため熱がこもりにくく、しかもデザインの質感も犠牲にされていませんでした。
その時は「最初からこれを選んでおけばよかった」と心底思いました。
空気の流れって、本当に大事です。
電源もまた不可欠な要素です。
高負荷時に必要な電力を供給できないとシステムが一瞬止まることすらあります。
私は過去に容量ギリギリの電源を使ってしまい、ゲーム中に突然画面がフリーズして心臓が止まりそうになった経験があります。
その時の冷や汗は今も忘れられません。
それ以来、余裕を持って850W以上の信頼できる電源を選ぶようにしています。
ここはどうしても削れない部分だと強く思っています。
ソフト面の工夫も快適さには大きく影響しました。
配信時にエンコード処理をGPUに任せるだけでも、CPUの余裕が一気に増して安定感がまるで違うんです。
さらに最近のNPUを活かすことで、ノイズの除去や映像の自動補正がスムーズに走り、結果的に見栄えも良くなる。
小さな調整ではありますが、それが積み重なって初めて「気持ちの良い一台」になっていきます。
最終的に私が声を大にして伝えたいのは、Core Ultra7 265Kは確かに優れたCPUですが、それ単体で魔法のように理想の環境が完成するわけではないということです。
逆にどこか一つを軽く考えると、その小さな穴が全体の快適さを壊してしまいます。
「準備がすべてだったな」と今になって思います。
これが私にとっての答えです。
配信を意識した場合にCore Ultra9と比べて見える差
配信用途を考えた場合に、私が実際に感じたのは「Core Ultra7 265Kでも十分こなせるけれど、より本格的に配信を突き詰めたいならCore Ultra9 285Kを選ぶほうが後悔は少ない」ということです。
正直に言って、ゲームプレイに限ればUltra7で困るシーンはほとんどありませんでした。
ただ、配信を前提に組み立てると事情が変わってきます。
長時間配信を続ける中で映像の細かな乱れや、エンコードの僅かな余裕不足が表に出てきて、これは視聴者にとって不意に気になる瞬間へと繋がるわけです。
その差が想像以上に響くのだと、身をもって経験しました。
実際に私がUltra7 265KとRTX5070Tiを使って4K配信を試した時、数時間を超える配信では一部のゲームでフレームが落ちて、見ている人から「ちょっと滑らかさが欠けてたね」と感想をもらったことがありました。
自分としても小さなカクつきに気づいた瞬間、せっかく観てくれている人に申し訳ない気持ちになったんです。
もちろん設定を下げるなどの調整は可能で、ある程度は対応できました。
でも、配信の世界は視聴者が大手ストリーマーやプロの高品質映像を当たり前に見慣れている時代ですから、「これくらいで十分」と割り切りにくい現実があるんですよね。
同じようにUltra9で試したときは、正直一気に肩の力が抜けました。
小さな差かもしれませんが、映像が安定して途切れず流れてくれる安心感がそこにはありました。
仕事を任せた同僚が、最後まできっちりやり抜いてくれたような感覚です。
こういう信頼感の積み重ねは、長期的に見れば圧倒的に大きな差になっていきます。
ゲームプレイそのものに関してはUltra7が本当に優秀です。
余力をもって動いてくれるので、裏で軽めの録画や資料用の動画編集も同時に回して問題ない場面が多いのはたしかです。
しかし配信を前提にしたとき、やはりエンコード処理の負荷に余裕があるUltra9のメリットははっきりしてきます。
これは単に数値上の比較ではなく、AI機能を同時稼働させた場面でも実感として違いが出ました。
例えば背景のノイズ除去や顔トラッキング、これを複数オンにした状態でUltra7だと息が上がるような重さを感じる瞬間があります。
一方Ultra9では滑らかに分散処理されていて、動作感が安定している。
配信者側としては声が途切れず映像が乱れないということが何より大事で、その部分を任せられるのは非常にありがたいものです。
けれど現実的な話として、価格の壁も大きく存在します。
Ultra7は間違いなくコストパフォーマンスに優れています。
フルHDやWQHD程度の配信なら、ほとんど不安なく快適に進められる。
それでいて値段が抑えられるわけですから、趣味の範囲でゲーム配信を楽しむ人にとっては無理のない選択肢です。
私自身も、夜中に趣味で放送をしたときUltra7は静音性も高くて「これで十分だ」と満足できました。
ケースにお気に入りの素材を取り入れて飾り気を楽しんだり、見た目にも気持ちの上がる時間でした。
この辺りは、まさに大人の理性的な選択と言えますね。
満足できる環境を無理なく作る。
大切な価値観です。
ただ、本気で商業イベントや外部に見せる配信を行う場面になると、Ultra9の一択だなと痛感しました。
ある現場でUltra9を搭載した機材を使ったとき、数時間を超える配信で一度も不安を感じずに進められたのです。
映像も音声も黙々と安定を保ってくれる姿に、まるで信頼できる上司の背中を見ているみたいな安心がありました。
その空気感は参加者にも伝わり、会場全体が落ち着いた空気に包まれたように思います。
やはり信じて任せられる性能というのは、現場全体に影響するんだと実感しました。
視聴者の目は確実に年々肥えてきています。
無料で高品質な放送を見られる時代では、個人の配信であっても視聴者は無意識にその水準を求めてしまう。
だからこそ、今後長期的に配信を続けていくつもりがあるならば、最初から性能に余裕のある機材を選んだ方が「後で買い替えなくてよかった」と思える可能性が高い。
私自身、何度も配信を重ねるたびにその視点の変化を感じました。
最終的には、フルHDやWQHDでの配信ならUltra7で十分満足できますし、4Kや複数同時配信を狙うのであればUltra9に軍配が上がります。
要は、どんな規模でどんな意味を込めて配信を行うのか。
そこを明確にして選ぶのが一番だということです。
安心して任せられる相棒。
そう言えるマシンをどう選ぶかは、これから先の自分の使い方に正直になることから始まります。
本当に必要なのはどこまでの安定感なのか、自分にとって大切にしたいのは配信の見栄えなのか、あるいはコストとの均衡なのか。
そこを丁寧に考えたとき、自分なりに納得のいく一台を選べるのだと思います。
重量級ゲームや複数アプリを同時に動かしたときの挙動
重量級のゲームを配信まで含めて思う存分楽しみたいなら、Core Ultra7 265Kを中心に環境を整えることがベストな選択だと私は感じました。
実際に自分で組んで試した結果、複数のアプリを同時に走らせても快適そのもので、ただスペック表を眺めていたときの印象をはるかに超える体験ができたからです。
私が改めて驚かされたのは、重量級タイトルを高画質設定で動かしながら、裏で配信ソフトやブラウザ、ボイスチャットまで同時に立ち上げても一切処理落ちを感じなかった点です。
以前なら設定を落として妥協しながら遊ぶのが当然だったのに、今は違う。
キャラクターの動きは終始滑らかで配信も安定、余計な気を使う必要がありませんでした。
実際にRPGの大規模マップを読み込むときも、かつては数秒単位の待ち時間を我慢し、「早く動いてくれよ」と心の中で呟いていたものです。
しかし今回の構成ではロードが一気に短縮され、気持ちの流れを止められることがないのです。
遊ぶ側にとって小さな快適さは積み重なると大きなストレスの差になる。
この違いは、ビジネスの現場で例えるなら、会議資料の表示に毎回数秒待たされるか否か、その程度の差ですが、積み上げれば集中力や成果の質に直結する重大な要素なのです。
特にイベント前、私は意図的に過酷な条件をつくったことがありました。
重量級のRPGを立ち上げ、配信画面の裏で動画素材を走らせ、さらにDiscordで仲間と会話。
ところが結果は正反対で、しっかり動作し続けてくれた。
その瞬間、心の底から頼もしさを感じたんです。
数年前の自分なら考えもしなかった光景でした。
もちろん、ただCPUを導入しただけでは最大限の力を発揮できません。
私自身、DDR5のメモリを32GB積み、システムにはNVMe Gen.4 SSDを採用しました。
その効果ははっきり目に見え、ロード時間が明らかに減り、シーン切り替えでも一切の引っ掛かりがなくなる。
そして見落としてはいけないのが冷却の存在です。
高性能なパーツを積めば当然ながら熱は出ます。
私は最初「標準的な空冷で大丈夫だろう」と考えていました。
しかし、実際にはDEEPCOOLの大型クーラーを導入して本当に良かったとしみじみ思います。
配信を続けて何時間も負荷をかけても安定する。
あの安心感は経験して初めて分かるものでした。
もしここをケチっていたら、突然の強制終了に頭を抱える羽目になっていたでしょう。
SSDについても同じことが言えます。
Gen.5は確かに速いですが、冷却が不十分なら逆に性能が落ちる恐れがあります。
そこで私は堅実にGen.4を選びました。
数値的には劣っても、安定性の確保こそが肝心だからです。
結果として動画編集も配信も問題なくこなせるので、大局的に見ればこの選択が正解だと納得しています。
こういう場面で感じるのは、結局は「バランス」なんですよね。
最新のAAAタイトルを遊ぶときの快適さは、単なる性能の証明以上に特別な意味を持ちます。
操作していてもラグがなく、CPUのPコアとEコアが自然に分担していて、ゲームはスムーズに動き、裏で複数アプリが走っても気にならない。
余裕を常に感じさせるこの挙動こそ、使い手に安心を与えてくれます。
一度体験したら、もう昔の環境に戻ろうなんて思えません。
ただし誤解しないでほしいのは、万能ではないという点です。
4Kや高リフレッシュレートを突き詰めるなら結局はGPUの力が不可欠です。
CPUがいくら優秀でも、GPUの性能不足だけは覆せません。
ここは過信せず、冷静に追加投資を検討することが必要です。
私はこの認識を常に持っています。
仕事でも同じで、優秀な人材がいても、周囲の環境を整えなければ成果は出せないものですから。
改めて振り返ると、このCore Ultra7 265Kのおかげで私のPC環境は大きく変わりました。
重量級ゲームも配信も共存できる新しい当たり前を与えてくれた。
複数アプリを同時に立ち上げても揺るぎない安定感を確保でき、そして何より余裕を感じさせてくれます。
私にとって答えは明確でした。
このCPUを組み込むことで「楽しく快適に遊びながら、同時に配信までこなせる」理想的な環境が整うのです。
心地よさ。
この二つが揃ったときに、初めてゲーム体験は心から豊かなものになると私は信じています。
Core Ultra7 265KゲーミングPCに合わせたいグラボ選び
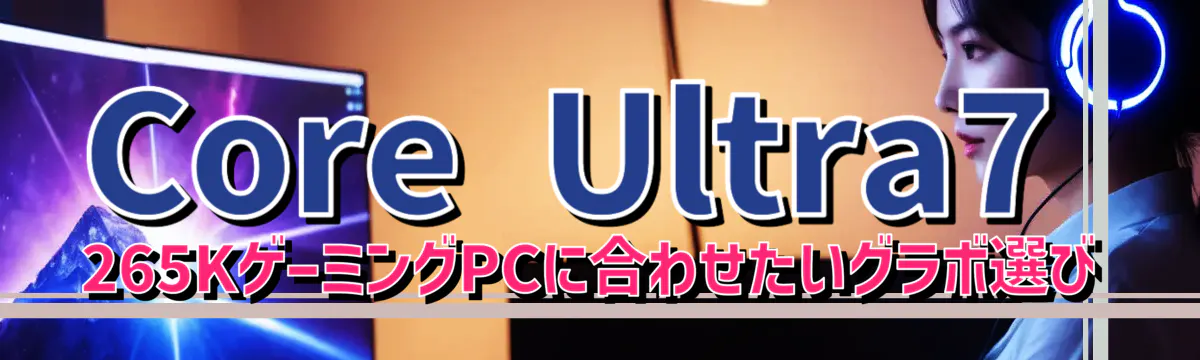
RTX5070TiとRX9070XTで実機テストから見えた性能とコスパ
単なるスペックの比較では見えてこない部分が多く、実際に触れて確かめてみることで初めて分かる安心感や違和感があるのだと思います。
正直に言えば、どちらも魅力を持つ一方で、条件次第で大きく印象が変わりました。
まず、私が特に強く感じたのはFPSのゲームでの違いです。
RTX5070Tiの安定感は頼もしいもので、ゲームをしながら配信ソフトを同時に動かしてもフレームが乱れにくく、視聴者側の配信画面が非常に滑らかでした。
私は夜な夜なゲーム配信をしているのですが、視聴者から「見やすいし途切れない」と言われた瞬間、心から報われた気がしました。
これは数字やベンチマークでは表現しきれない体験で、やっぱり使ってこそ分かる世界です。
それに対してRX9070XTは、圧倒的に価格面での強みがあります。
ミドルレンジ帯に位置しながらFSR 4によって高解像度環境でも十分なフレームをキープする。
その実力は確かで、モンスターハンターの新作を試したときには「あれ、Radeonってこんなに改善されてたのか」と口にしてしまったほどです。
昔の世代では不安の残る部分が多かっただけに、その変貌ぶりには正直驚かされました。
良い意味で裏切られた気分です。
ただ、ひとつ気になるのは発熱です。
RTX5070Tiは比較的落ち着いて温度が推移しますが、RX9070XTは長時間高負荷をかけると温度が目立って上がります。
私自身、過去に冷却を軽視してPCが不意に落ちてしまった苦い経験があり、今ではケース内のエアフローを軽んじることはありません。
最近流行のガラスパネルケースでは特に、冷却ファンを増設するかどうかで安定性が大きく変わると実感しました。
熱対策は軽視できませんね。
消費電力についても差が出ました。
RTX5070Tiは必要な電力量が比較的抑えられており、電源ユニットの選択にも余裕が持てる安心感があります。
一方、RX9070XTはピーク時の消費が大きく、それなりの電源を用意しないと不安になるという印象でした。
省エネに優れるということは、結局長期的に見れば選択の決め手になり得ます。
配信を中心に考える私にとっては、RTX5070Tiに軍配が上がりました。
やはりNVENCによるエンコード品質が安心できるレベルで、視聴者に対して安定した画を見せられることは大きな意味を持ちます。
私にとって配信が趣味であると同時に大事な繋がりである以上、ここを妥協するわけにはいきませんでした。
しかし正直に言えば、RX9070XTの高フレームレート性能や快適さにも心を揺さぶられました。
「これは思ってた以上に良いじゃないか」と心の中で呟いてしまったのです。
期待を超えられると、嬉しくなってしまうんですよね。
用途の違い。
配信や動画編集も視野に入れるならRTX5070Tiが安定し、逆に純粋なゲームの快適さやコスト意識を優先するならRX9070XTの方が理にかなっています。
自分がPCに何を求めているか、これを明確にした時に選択は自然に決まってくるのでしょう。
PCのパーツを選ぶことは単なる性能比較ではなく、自分の生活や趣味のスタイルを映し出す行動だとあらためて思いました。
性能を追いかけるだけでなく、どう付き合うのかが選択の軸になるのです。
信頼できる相棒。
そして安心して使える環境。
どちらのカードも、その価値を実際に手で体感できる存在でした。
今回改めて、自分の求めるスタイルを整理して選んだ結果だからこそ、納得感とともに満ち足りた気持ちになれたのだと思います。
4K配信を見据えるなら押さえておきたいGPUの基準
もし私がこれから4K配信に備えて機材を整えるとしたら、やはり一番重視すべきはグラフィックボードだと考えています。
フルHDで楽しんでいた頃には「そんなに性能の差が体感に出るのか?」と半信半疑でした。
しかし4Kに挑戦してみたら、その考えは甘かったと痛感しました。
スペック表では見えない余力の有無が、実際には映像の滑らかさや配信の安定性を左右する。
やっぱりある程度以上のGPUを選ばなければダメなんだ。
これが私の実感です。
具体的に言えば、RTX 50シリーズやRadeon RX 90シリーズのうち、少なくともミドルハイクラス以上が現実的な選択になります。
4K配信は単にゲーム映像を出すだけでなく、同時にエンコードや配信ソフトの制御も走ります。
正直「ゲームが動くから大丈夫」と思って選んだGPUでは配信になった途端に挙動が怪しくなり、視聴者にはカクついた映像を見せてしまう。
私はその失敗を何度も経験しました。
以前RTX 5070を使って配信を試した時のことです。
ゲームは快適に動いていたので「これなら十分だろう」と高をくくっていました。
コメント欄に「映像止まってませんか?」と指摘された時の気まずさといったら、本当に情けなかった。
そのあと結局5070Tiに買い替えたらようやく安定して動作し、初めて「なるほど、やっぱりギリギリじゃ通用しないのか」と分かったんです。
この時の悔しさは今でも忘れられません。
教訓ですね。
周辺の仕様もまた軽視できません。
DisplayPort2.1対応なら4K144Hzでも余裕があるし、PCIe5.0の帯域が確保されていればCPUとGPUのやり取りで無駄な待ち時間が発生しにくい。
私は以前このあたりを考慮せず、せっかく高価なCPUを導入したのにGPUや接続規格が足を引っ張り、全然性能を引き出せなかったことがあります。
宝の持ち腐れでしたよ。
あの時の後悔は二度としたくない。
さらに最近ではAI支援の力も無視できません。
DLSS4やFSR4のような技術があると、映像の美しさを維持したまま処理負荷をグッと軽くできます。
これは4K配信において本当に大きな差になります。
CPUにもNPUが積まれてGPUと協調することで、映像がよりスムーズに流れる未来がもう現実になりつつあるのです。
私は実際それを体感し、正直少し感動すらしました。
こうした最新の進化を取り入れるかどうかで、数年後に大きな差が出ると確信しています。
そして地味に驚かされたのがRadeonの進化です。
昔は正直ここまで期待していなかったのですが、RX 9070XTを試した時の安定感は「おや?」と思わず声が出るほどでした。
FSR4を有効にするとビットレートがしっかり安定し、映像の品質も高水準を維持できる。
CUDAサポートがない分は工夫が必要ですが、そこを割り切れば十分候補に入ります。
最終的に私が行き着いたのは、RTX5070Ti以上かRX9070XT以上を選ぶことです。
ここを下回ると、設定を少し上げただけで途端に配信が乱れたり、ソフトが重くなったりしてしまう。
Core Ultra7 265KのようなCPUを導入しても、GPUの力が不足していたら結局バランスが取れない。
これは遠回りした末に得た答えです。
配信を見に来てくださる方にストレスなく楽しんでもらいたい。
だから私は妥協せず選ぶようになりました。
初心者のころはつい費用を抑えようとして「まあこの程度でいいだろう」と中途半端なモデルを選んでいましたが、結局二度買い三度買いになり、金銭的にも時間的にも損をしました。
やるせない経験でしたね。
今思えば、余裕のある仕様を最初から選んでおくのが一番の節約です。
安心して使える相棒を持つこと。
それが本当の意味でのコストパフォーマンスにつながります。
長く使える。
安定する。
これこそが最大の価値です。
私が最終的に伝えたいのは、派手な数字に惑わされるよりも、実際に余裕を持って動き続けられる機材を選ぶことの大切さです。
それなら迷わず一定水準以上のGPUを選んでほしい。
これが、走り回った末にたどり着いた、私の答えなんです。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48655 | 102452 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32127 | 78469 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30130 | 67099 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30053 | 73798 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27143 | 69279 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26486 | 60545 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21934 | 57089 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19905 | 50739 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16548 | 39572 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15982 | 38394 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15845 | 38170 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14628 | 35097 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13733 | 31016 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13193 | 32525 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10814 | 31904 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10643 | 28730 | 115W | 公式 | 価格 |
265K搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55HS

| 【ZEFT Z55HS スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5080 (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54AQS

| 【ZEFT Z54AQS スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54EBA

| 【ZEFT Z54EBA スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55EKA

| 【ZEFT Z55EKA スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54DQ

| 【ZEFT Z54DQ スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal North ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
DLSSやAI補助機能を使った実際の快適化体験
正直にお伝えすると、私は最新のCore Ultra7 265Kと新世代のグラフィックボードを組み合わせたとき、やっと本当に落ち着いてゲームを楽しめる環境になったと実感しました。
これまで長時間プレイすると必ずフレームレートが不安定になり、少しストレスを感じていたんです。
特にDLSS 4を有効にした瞬間の鮮明な映像の変化には思わず「これはすごいな」と声が出てしまったほどです。
レイトレーシングをしっかり効かせた状態で不安なく遊べる喜び。
この安心感は格別でした。
配信をしながら遊ぶ私にとって、AI補助の存在は技術的な強みというだけでなく実務的な安心にもつながっています。
本来であればCPUがフル稼働して動作が不安定になりがちな箇所も、NPUが陰で支えてくれることで負荷の偏りが和らいでいるのでしょう。
配信中に映像がカクつかずスムーズに流れていると、「やっと落ち着いてできるな」という気持ちになれます。
レイトレーシングを効かせていてもフレーム維持ができ、DLSSによる高解像度の鮮明さも見事。
大画面に描かれるそのシーンは、言葉にすると簡単ですが、実際に自宅のリビングで体験すると本当に息をのむような迫力です。
仕事を終えて深夜にプレイするとき、「ここまできれいに動くのか」と思わず小さく唸ってしまいました。
ゲームとしての世界観に没頭させられる感覚。
過去の自分の環境からは考えられなかった満足感です。
これは心を豊かにする時間そのものです。
ただ、もちろん良いこと尽くしではありません。
AIの自動補正が効きすぎているのか、人物の輪郭が妙に強調され、ちょっと違和感を覚える場面もありました。
率直に言えば「余計なことをしないでほしい」と感じた瞬間もあります。
完璧でなくてもいい。
進化の過程を楽しむ気持ちで受け止めれば、不思議と余裕さえ感じられるんです。
その価値がもっとも発揮されるのは、やはり配信の場面でしょう。
画質の低下や映像遅延が減れば、視聴者にストレスを与えずに済みます。
自分自身も冷や汗をかかずに気持ちよく続けられる。
期待と安心、両方を感じられる今の延長線上にこそ次の楽しさがあるのだと信じているからです。
実際に利用してみて、私が率直に感じたのはCore Ultra7 265KとRTX 5070 Tiクラスの組み合わせが性能と価格のバランス面で「ちょうどいい」ということでした。
高価な上位モデルを狙おうと思えばいくらでも上があるのですが、趣味として冷静に考えると、このあたりの構成で十分に大きな満足を得られるんです。
映像や動作が快適そのもので、さらにAIやDLSSでパフォーマンスを底上げする余地まである。
「現行ベスト」と胸を張って言えるのは、この安心できる手応えのおかげです。
上を追いかけ過ぎるのは危険。
それを忘れないようにしています。
私としての結論は明快です。
Core Ultra7 265Kを軸にAI補助に対応した最新グラフィックボードを選び、DLSSや配信補助を積極的に導入する構成こそが、現場でも家庭でも最もストレスなく楽しめる方法です。
もう迷う必要はありません。
安定した映像美と快適な動作を両立できる環境が、すでに自分の手に届くところにあるのですから。
その事実に気づいたとき、私は妙に清々しい気持ちになったのを覚えています。
これまで、私はパーツの組み合わせで何度も頭を抱え、ときには買って後悔したこともありました。
しかし今回の選択は違います。
自分のためにも視聴者のためにも、そして未来のゲーム体験を楽しむためにも、このAI補助と最新CPU・GPUの組み合わせは欠かせない存在になっていくでしょう。
私はそう信じています。
これこそが今の私にとって揺るぎない答えです。
Core Ultra7 265Kマシンに最適なメモリとストレージ構成
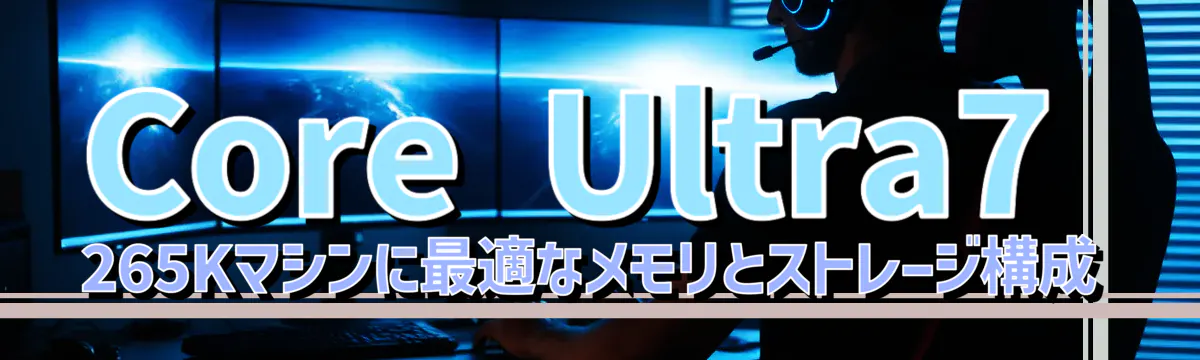
DDR5メモリは32GBで十分か、それとも64GBか
正直、ゲームだけが目的であれば32GBでまったく問題ありません。
最新の大作タイトルでも安定して動作しますし、単純に遊ぶだけなら「これで十分だな」と思えるレベルです。
ただし、そこに配信や動画編集を絡めると途端に様相が変わるんです。
私も過去に32GB環境で配信ソフトとPremiereを同時に動かしたとき、最初はいい調子で進んでいた編集作業が突然もっさりし始め、エフェクト切り替えのたびに数秒の待ち時間が出て正直イライラしました。
そのときの不快感はいまも忘れません。
だから私は迷わず64GBへ切り替えました。
その後の作業の余裕、この安心感。
これがあるかないかでは本当に仕事のリズムが違うんです。
動画編集をしていてもバックグラウンドで配信を流していても、処理が止まらない。
それだけで気持ちがずっと楽になりました。
とはいえ64GBが魔法の解決策かといえば、そうではありません。
現実的には発熱とコストが立ちはだかります。
DDR5は以前より効率が良くなったとはいえ、メモリを積めば積むほどケース内のエアフローや冷却設計が効いてきます。
ここで手を抜くと結局は安定しなくなる。
だから私はケースを選ぶのに時間をかけ、多少高くても冷却性能の高いファンを組み込みました。
この「冷える安心感」は、本当に実際に運用して体験してみないとわからない部分です。
妥協すると後悔しますよ。
CPUとしてのCore Ultra7 265Kは本当に強力です。
20コア構成で並列処理も余裕。
そのため足を引っ張るのはCPUではなく、意外なことにメモリです。
ゲーム側も配信側もスムーズに伸びやかにつながる感覚は、はっきり言って一度体験すると戻れなくなりますね。
もちろん「ゲームしかしない」という前提なら32GBで十分なんです。
いや、本当に十分なんですよ。
ただ、ひとたび動画制作やAIを用いた映像生成を組み込むと32GBでは足りなくなる。
なので私は環境を組むときに迷わず64GBを選ぶようにしました。
特にこれからのゲームは高解像度テクスチャや大規模データを要求してくる傾向が強くなっているので、長い視点で見ればこの選択はより合理的になっていくはずです。
将来性。
AIを活用した画像生成や動画編集補助ツールは、最近では一般的に手に届くようになりましたが、それらを同時に走らせればメモリはあっという間に食いつぶされます。
32GB環境だと途端に動作が不安定になり、思考が中断される。
あのストレスといったら、もうね…。
一方で64GBだと裏で複数アプリを立ち上げていても驚くほど作業が途切れません。
作業全体が滑らかに流れるように進む感覚は、私にとってちょっとした衝撃でした。
メモリモジュールそのものの選び方も忘れてはいけません。
私は昔ノーブランド品に手を出したことがあるんですが、これが最悪でした。
クロックを少しいじっただけで落ち、安定しない。
それこそ設定調整に時間を食われ、本来の目的である作業どころではありませんでした。
その後、Crucialに切り替えてから一気に安定。
安心して作業できることがどれだけ生産性を引き上げてくれるか、身をもって痛感しましたね。
ブランドを信頼する大切さ。
これも忘れてはいけません。
「でも64GBってやりすぎじゃない?」という声も確かにありますし、私も理解できます。
ただし長期的に考えると、新しいソフトや大容量ゲームが出るたびに「またメモリ不足か」と悩むのはもううんざりです。
そうした面倒を考えると、最初から64GBで固める方が明らかに楽。
これは投資、そう割り切っています。
繰り返しますが、答え自体は決して難しくないんです。
純粋にゲームだけなら32GBで問題なし。
でも配信や動画編集、そしてAIツールなどを組み込むなら64GBが正解です。
迷う必要はないんです。
自分のスタイルをよく見直して、自分で選び切るだけ。
そうやって環境を整えた瞬間に、不安はすっと消えていきます。
私にとって、それが何よりの満足につながっているのです。
安心感。
まさにこの一言です。
NVMe Gen.5とGen.4 SSDをどう役割分担させるか
パソコンの構成を考えるとき、私はまず「安心して長く使えるかどうか」を何よりも重視しています。
特に日常的に触れる場面でストレスがたまるのはどんなときかと振り返ると、やっぱりロード時間なんですよね。
ゲームでも配信でも、待たされているだけで気持ちが落ちる。
せっかく楽しむ時間なのに、そのたびに小さな不満が積もってしまうんです。
そんな中で初めてNVMe Gen.5を導入したときの衝撃は、本当に鮮明に覚えています。
重たいオンラインゲームでも画面の切り替えが流れるように進む。
あの瞬間の感覚は、今でも忘れられない。
とはいえ、全てのストレージをGen.5で固めようと考えるのは現実的ではありません。
熱の問題もあれば、コストの圧力も馬鹿にならない。
家庭を持つ立場からすると、高性能パーツを追加するたびに余計な心配が増えるのが正直なところです。
だから私は用途ごとに線を引きました。
システムやメインゲームはGen.5に任せ、他はGen.4に割り振る。
それが今の私にとって無理のない構成なんです。
負担を分散させることで、財布にも心にも少し余裕ができる。
妙にホッとする仕組みです。
一番効果を実感したのは録画データの扱いでした。
以前は一台の高速SSDに何もかも詰め込んでいたので、書き込みが増えるたびに寿命を案じる羽目になる。
配信をしていると「これ、あとで壊れたりしないよな」と妙な不安が頭をよぎるんです。
楽しみながらも背中に嫌な冷や汗…そんな感覚でした。
でも保存先をGen.4に分けるようになってからは、気持ちに明らかな違いが出ました。
無駄に酷使せずに済むし、コストも抑えられる。
「ああ、大人になったからできた選択だな」と思わず口に出してしまった。
Gen.4の良さは、一言で言えば堅実さです。
派手さこそないけれど、安定して動いてくれる安心感は何ものにも代えがたい。
仕事用のデータや家族の写真、失いたくない大切な記録。
そういう「絶対に失敗できないもの」ほど、私はGen.4に預けています。
不安が減って心が落ち着く。
頼れる同僚のような存在ですね。
一方でGen.5の魅力は、間違いなく瞬発力にある。
新しいゲームを立ち上げた瞬間、映像が切り替わる場面でまったく待たされない。
これがどれほどストレス軽減につながるか、やってみないと伝わらないかもしれません。
配信中にロードが長いと、視聴者が徐々に離れていくのが目に見えてわかるんです。
だから私は迷いなく、システムドライブとメインのゲームはGen.5で固めます。
テンポ感が全く違う。
そう言い切れます。
ただし現実を直視すると、Gen.5は価格もまだ高いし、冷却面でもなかなか扱いが難しい。
昔、冷却管理を甘く見たせいで不具合を起こした経験があるんですよ。
あのとき慌てて扇風機をケースに向けて必死にしのいだ姿を思い出すと、自分でも笑ってしまいます。
けれど同じ失敗は二度と繰り返したくない。
だから今は冷却とエアフローに人一倍気を遣っています。
その点、Gen.4はやはり心強い。
性能では劣るものの、価格は安定し、容量も気にせず選べる。
特に動画や仕事の記録がどんどん積み重なっていく40代の私にとって、現実と趣味を両立させるための後押しになるのはむしろGen.4なんです。
触れるたびに「ああ、しっかり備えてあるな」と安心できる。
この安心感は大きい。
でも配信しながらのゲームプレイには、やはり限界を感じる局面が出てきます。
ロードのわずかな遅延やカットシーン切り替えに引っかかりを感じると、視聴者もテンポの乱れを敏感に察知する。
ほんの数秒の差なのに、その積み重ねが大きな違いになるんです。
だから私はあえて役割分担にこだわります。
最終的に声を大にして伝えたいのは、メインにGen.5を置くことで実感できる快適さの大きさです。
応答の鋭さが時間の密度を変えてくれる。
その効果で配信もゲームも余裕を持って楽しめるんです。
そしてそれを補う形でGen.4を配備する。
この組み合わせならコストも抑えられるし、何より長期的に安心。
言葉にすると単純ですが、毎日の中で確実に違いを生んでくれる構成です。
将来的にGen.5の価格が下がるであろう未来は見えています。
でも今の私には、この二段構えこそが現実的で賢明な選択。
そう、落ち着ける日常こそ財産なんですよね。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
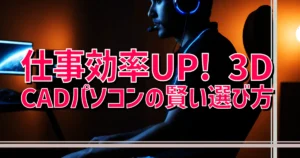
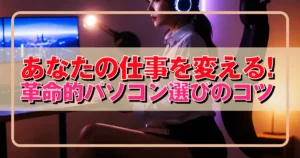
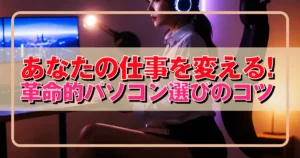
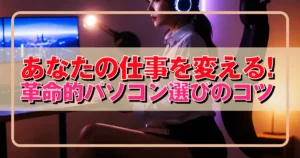
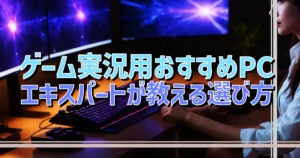
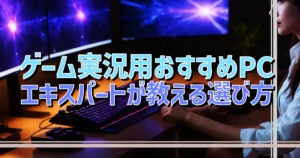
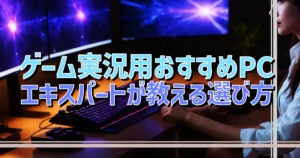
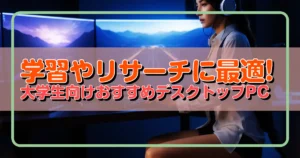
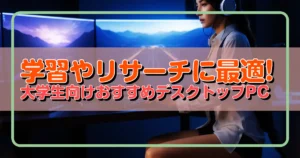
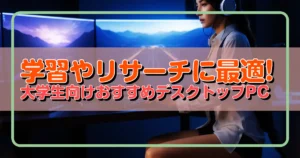
容量不足を避けるための現実的なストレージ組み方
ストレージです。
処理速度ばかり追いかけがちですが、使い込んでいくと「ストレージの容量が不足して作業が滞る」という現実にぶつかります。
そしてそれはゲームだけに限らず、仕事や生活のリズムにまでじんわり影響を与えるんです。
私は過去に実際そうした不便を味わい、せっかくの高性能PCが逆にストレスの種になってしまった苦い経験をしました。
近年のゲームは本当に容量が大きくなりました。
1タイトルでも100GBを簡単に超え、アップデートのたびに150GB、200GBと膨れ上がることも珍しくない。
しかもゲームだけでは済まないのが悩ましいところです。
実況配信や録画編集をやろうとすると、一気に動画データが積み上がっていく。
気付けば残り容量が数十GBしかない、そんな赤字警告を画面で見たことが一度や二度ではありません。
消すか、外付けに逃すか、あるいは急いで増設か。
これを繰り返していた時期は、正直うんざりしていました。
システムとアプリ専用のSSD1TBを速度優先で用意し、メインのゲームには2TB以上を割り当てる。
そして録画や編集データを保存するために、さらに2TBの専用ドライブを確保する。
私と同じように配信や動画編集に挑戦したいなら、ここは絶対に分けておくべきです。
実際私も以前、すべてを1本のSSDに任せていた頃はライブ配信の最中にフレームレートがガタ落ちし、視聴者から「カクついてるよ」と言われて冷や汗をかいたものです。
その後、録画専用のストレージを用意するだけで見違えるように安定しました。
原因がわかったときの衝撃は大きかったですが、「これか!」と納得した瞬間に思わず苦笑いしましたよ。
PCIe Gen.5の高速SSDも気になるのは確かです。
数値上の速度を見れば心躍るし、初めて使うときは笑ってしまうほど速い。
しかし価格は高いし、とにかく発熱が厄介。
本体を冷やすために大げさな冷却装置を追加するほどの価値が、今の段階であるのかと考えると私は懐疑的です。
私自身、Gen.4の上位モデルを使っていますが、ロードやアップデートも十分高速で不便を感じることはありません。
現実的にはGen.4で必要十分、むしろコストとのバランスを考えるとベストだと感じています。
でもそれは後から面倒を生むことが多いのです。
実際、一度組んだケースを開いて内部レイアウトを組み直し、熱対策やケーブル位置を再調整するのは骨が折れます。
大事な休日をそれに費やす徒労感といったらありません。
容量をけちった結果、繰り返す作業に悩むよりも、最初の投資で精神的ゆとりを買うほうが断然いいです。
2TBのゲームストレージは驚くほど簡単に埋まります。
特にここ数年のAAAタイトルは肥大化がすさまじい。
私は現在、OSとアプリ用に1TB、メインゲーム用に2TB、録画や編集用に2TB、この3本で運用しています。
残容量を気にせずにすむ環境。
インストールするたびに「どれを削除するか」と悩まなくなり、小さなストレスがなくなったことで日々の充実感まで変わるのです。
大げさかもしれませんが、本当にそう感じます。
Core Ultra7 265KとRTX 5070Tiを組み合わせた立派なマシンを作ったのですが、ストレージは1TB+1TB。
半年もたたないうちに容量切れに追い込まれ、結局大掛かりな増設とデータ移行を余儀なくされました。
その作業に疲れ切った様子を目にして、私は心の中で「やはり最初から余裕を取っておくに限る」と強く思わずにはいられませんでした。
動作の快適さを支える土台です。
私は合計4TBを最低ラインとして推奨します。
本音を言えば5TB程度あるともっと安心です。
1TBをシステム、2TBをゲーム、2TBをデータ保存。
この三段階が私の経験上最適で、数年間安心して運用できるもっともバランスの取れた構成だと考えています。
余裕のある構成。
これが日々の満足感に直結するのです。
だからこそ、最初に妥協してはいけない。
ケチった結果の後悔ほどつまらないものはありません。
最初の段階でしっかりと未来を見据えたストレージを組む。
それによって余計な悩みから解放され、自分の時間を本来やるべきことに集中して使えるようになるんです。
Core Ultra7 265KゲーミングPCを冷やすための選択肢とケース選び
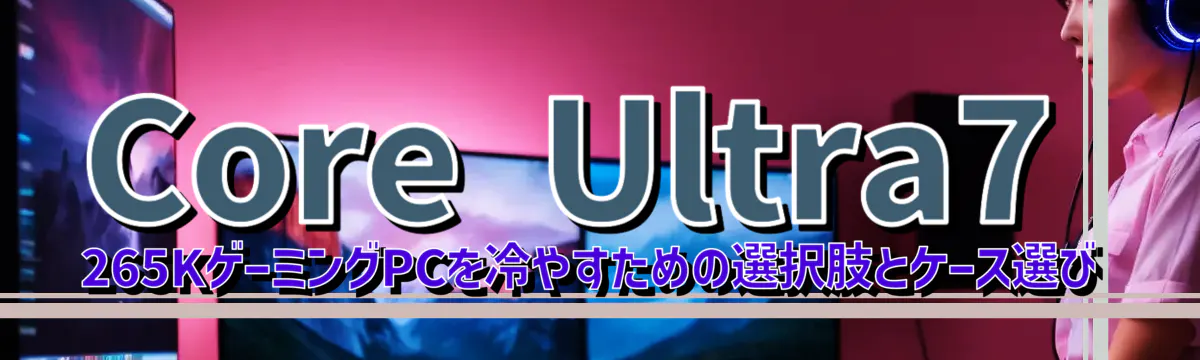
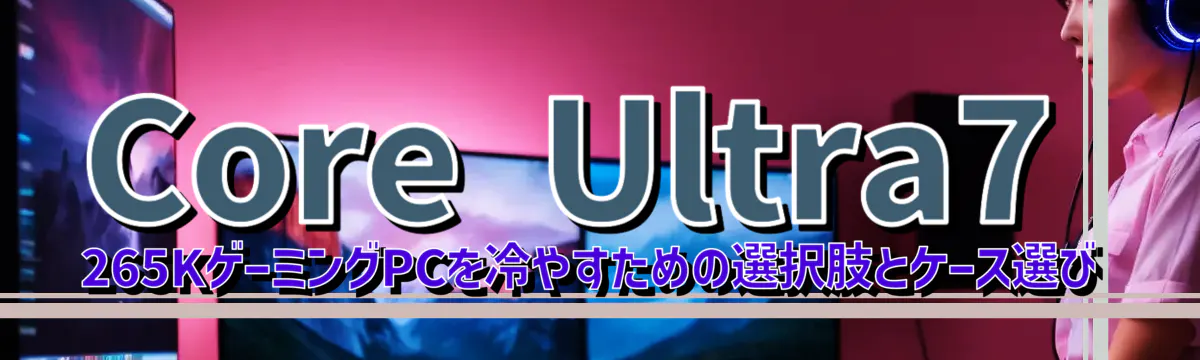
空冷と水冷を選ぶときに押さえておきたい判断材料
性能と安心感を求めるなら空冷、限界性能まで引き出したいなら水冷。
そう言い切れるほど、自分の経験の中で両者の違いははっきりしているのです。
設置も簡単でメンテナンスの負荷も少ない。
これは、長く付き合う人間からすると非常にありがたいものです。
私自身、出張の多い生活をしており、パソコンに余計な手間をかける時間は限られています。
それでも空冷なら掃除機で軽くホコリを吸い取ってやるだけで十分に性能を維持できるので、気兼ねなく使い続けられる安心感があるのです。
シンプルだからこそ信頼できる。
その一言に尽きます。
Core Ultra7 265Kは前世代よりも発熱が抑えられてはいますが、クロックを上げれば当然熱が溜まります。
静かで、堅実。
昔からの定番に理由があるのは事実だと実感しています。
しかし一方で、水冷の強みを目の当たりにしたときの衝撃も忘れられません。
360mmラジエーターを使ったときの冷却力は圧倒的で、真夏でもCPUの温度は安定して、4Kゲーミングを長時間行っても不安がなくなりました。
私はかつて水漏れに強い不安を抱いていましたが、近年は改良が進んでおり、耐久性もしっかり配慮されています。
昔とは事情が違うのだな、と安心しました。
初めて電源を入れた瞬間、CPUだけでなくGPUまで温度が落ち着いたのを見て「これは別物だ」と声が出ました。
効率がここまで変わるのかと体感した経験は、いま振り返っても強烈でしたね。
ただし、静音性に関しては多くの人が誤解しているのではないかと思います。
水冷だから全てが静かというわけではありません。
実際にはポンプの作動音がかすかに耳に残ることがあります。
この「かすかに」というのが曲者で、気にならない人もいれば妙に神経に触る人もいる。
正直なところ、人を選ぶのです。
一方で、大型の空冷ファンの中には恐ろしく静かなモデルもあり、深夜の作業中に耳を澄ませなければ動作を感じ取れないほどです。
この静けさは、一度味わうと手放せないですね。
導入の容易さも比較対象として明確です。
空冷はCPUソケットにしっかりと固定するだけ。
最初に自作を挑戦する人にとって、このシンプルさは心強い味方です。
水冷になると事情がガラッと変わり、ラジエーターの置き場やケースの相性を前提に考える必要があります。
最近人気のガラス張りケースは見た目はスタイリッシュですが、ラジエーターを前面に配置したら吸気が不足してしまうこともあります。
私は過去にこれで失敗し、泣く泣くケースを買い替えた経験があります。
だから今でも水冷導入を検討するときは、慎重に相性を確認するようにしています。
用途ごとの差も重要です。
動画編集や配信など長時間の高負荷作業を前提にする方には水冷を勧めます。
逆にライトにゲームを楽しむ程度なら空冷で十分です。
その違いを理解せずに「とにかく水冷のほうが良い」と思い込むと、結果的に無駄な投資になりかねません。
GPUの発熱は年々増えています。
同じCore Ultra7 265Kでも、例えばRTX 5070 Tiクラスと組み合わせるならケース内の空調は無視できない要素です。
CPUの冷却だけに目を奪われるのは危険で、ケース全体の熱設計を考えないと性能が頭打ちになります。
これを実体験で学んでからは、冷却方式の判断を単純なCPUの話に留めなくなりました。
機械は全体で動いている。
そういう感覚を大事にしています。
私が理想とするのは、空冷の手軽さと水冷の冷却力を組み合わせたハイブリッドのような仕組みが一般的になる未来です。
最近はモジュール式の自由度の高いケースが増えており、見た瞬間に「これなら空冷と水冷を状況で使い分けできるのでは」と想像してしまうことがあります。
そうした柔軟さが当たり前になれば、多くの人が悩まず自分に合った選択をできるはずです。
最終的にどうするべきかをはっきり伝えます。
私の体験から言えば、基本的にCore Ultra7 265Kは大型空冷で問題なく楽しむことができます。
ただし、4K配信や編集作業などの過酷な場面を想定しているのであれば、迷わず360mm以上の水冷を勧めたい。
これが日々使用して得た私の答えです。
冷却方式の選択に正解は一つではありません。
大切なのは、自分のライフスタイルにフィットし、毎日安心して使えるかどうか。
私はその観点で選ぶことこそ、後に悔いを残さない最良の方法だと実感しているのです。
だからこそ。
265K搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54ATC


| 【ZEFT Z54ATC スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54Z


| 【ZEFT Z54Z スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN SR-u7-6170D/S9


| 【SR-u7-6170D/S9 スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56BP
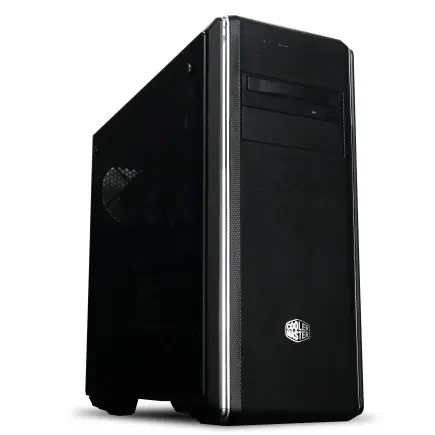
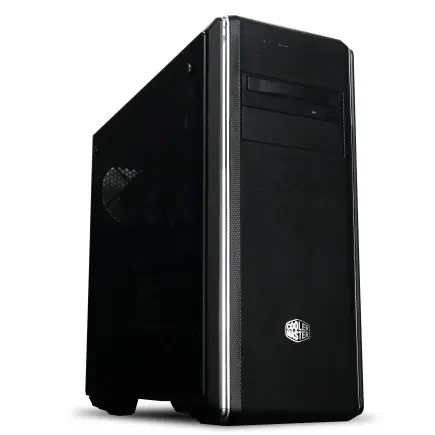
| 【ZEFT Z56BP スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | クーラーマスター MasterBox CM694 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55BY


| 【ZEFT Z55BY スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
ケース選びで失敗しないためのエアフロー設計の見方
これは机上の理屈ではなく、身をもって経験したからこそ言えることです。
見た目を重視したケースを選んで失敗し、ゲームや動画編集中に発生した熱に振り回されたときの焦りと苛立ちは、今となっては忘れられない教訓になっています。
冷却が整っていなければ、せっかくの投資が無駄になってしまうのだと骨身に染みました。
当時の私は、外観に惚れて選んだガラスパネルのケースに胸を弾ませていました。
けれど、実際に使用してみると、吸気不足でCPUの温度はすぐに上昇し、GPUのファンも狂ったように回り続ける。
夜中の静けさにその騒音が際立ち、「ああ、これは完全に失敗したな…」とため息をつきました。
見栄えだけに引っ張られてしまった自分を、正直情けなく思いました。
格好より中身。
これが結局の真理なんだと痛感しました。
フロントからたっぷりと空気を吸い込み、リアと天面から効率的に熱を放出する。
この自然な流れが実現できなければ、夏場や高負荷時はあっという間に限界が来ます。
特にCore Ultra7 265Kのようにゲーム配信と動画編集を同時進行するようなヘビーな使い方では、冷却が追いつかないと性能が落ち込みます。
その瞬間に感じる動作の鈍さと落胆は本当に辛いものです。
「性能より冷却が第一だ」と思い知らされました。
最近のケースはガラスやライティング重視のモデルが多く、SNS映えする見た目には魅力を感じます。
ただ残念ながら、冷却効率を犠牲にしているものも多いのです。
私も一度、RGBライティングを前面に強調したケースに惹かれて購入しましたが、実際には吸気不足で、ゲームを数分遊べば内部は熱を持ち、期待していた快適さはすぐに失望へと変わりました。
光るだけで肝心のパフォーマンスが台無し。
あのときの「見た目に釣られた自分が恥ずかしい」という気持ちは、今の私を冷静にしてくれています。
派手さではなく安定感。
大人ならではの選び方。
ケースを選ぶうえで一番確認すべきなのは、吸気口の位置とサイズです。
その次に重要なのがフィルターの有無。
ほこりが積もって空気の流れを阻害すると、冷却性能が徐々に落ちるばかりか、長期的にパーツ寿命まで縮めてしまう。
私は過去に掃除を怠ったためにファンが固まり、内部が熱地獄になった経験があります。
だからこそ、今はケースを買うときに必ず吸気経路と排気経路のスムーズさを確認します。
これは理屈ではなく、実際に手を動かして痛い目を見たからこそ覚えた判断基準です。
天面設計の重要性も無視できません。
簡易水冷を取り入れるならラジエーターの設置スペースを、空冷なら自然対流できるスリットの有無を確認するべきです。
この違いだけで高負荷時の安定感が大きく変化するのです。
一度この点を軽視して後悔したのですが、それ以降はケース選びの最初のチェックポイントにしています。
熱を取り込む場所と逃がす場所、この両輪が整っていれば、遊んでいるときに「温度は大丈夫か」なんて余計な心配をせずに済む。
それが本当に大きな安心につながります。
最終的に選ぶべきケースは、私は迷わずフロントメッシュ構造だと考えています。
正面からしっかり吸気できて、少なくとも2基以上のファンを設置可能、さらに天面からきちんと排気できる。
この条件さえ揃えば、Core Ultra7 265Kの実力を安定して引き出すことができます。
見た目はもちろん大切ですが、優先順位は冷却が一番、その次にデザイン。
私はそういう順に切り替えました。
その方が長く付き合ったときの満足度が桁違いなんです。
静音性。
快適さ。
高額なCPUやGPUを導入したにもかかわらず、ケースによる冷却不足でクロックダウンしたときの失望感は計り知れません。
だからこそ、私はケースを単なる「箱」と見なさず、PC全体を守る心臓部だと感じています。
自作PC歴が長くても、こうした当たり前の事実に気づくのに時間がかかるものです。
仕事で効率を追求してきた40代の自分にとって、PC選びでも「効率を阻む要因を取り除く」という視点がそのまま通用することに気づきました。
もしこれから新しくPCを組み立てたいと考えている人がいるなら、私は強く伝えたいのです。
性能を支えるのはケースと冷却設計だと。
CPUやGPUに投資する喜びは大きいですが、それを最大限楽しませてくれるのは裏側で粛々と働くエアフローの存在です。
見た目に惑わされず、しかし心の熱を持ちながらケースを選んでほしい。
大切なのは派手さではなく、確かな冷却設計。
それを忘れなければ、PC生活はもっと豊かで楽しいものになるはずです。
静音と冷却を両立させるケース選びのコツ
ゲーミングPCのケースを選ぶ上で、私が何よりも大切だと考えているのは「静音と冷却の両立は十分に可能だ」という事実です。
相反して見える両者ですが、ケース設計やファン配置の工夫次第で、実際にはそのバランスはうまく取れます。
自作を繰り返すたびに痛感したのは、静かにも冷えもしない環境でのストレスの大きさです。
苛立ちを覚えながらゲームをしたり、作業を中断せざるを得なかったこともありました。
だからこそ、最初のケース選びが後々の快適さや安心感に直結するのだと強く実感しています。
ケースを選ぶ際に基本となるのは、吸気と排気のバランスです。
フロントからの吸気、リアとトップからの排気、この仕組みが十分に機能してこそ最適な循環が生まれます。
しかし、デザイン重視で選んだ結果、吸気口が小さく熱がこもるケースも少なくありません。
かつて一度、私も外観の美しさに惹かれて購入したケースで失敗しました。
確かに見た目には満足しましたが、プレイ中に轟音のように鳴り響くファン音には耐えきれず、結局短期間で買い替えることになったのです。
最近はガラスパネルを採用したケースが主流になっていて、LEDを搭載した内部パーツを美しく演出でき、部屋のインテリア性を高める点は魅力的です。
ガラスタイプを選ぶ場合、フロントやボトム部分で十分な吸気が確保できるかどうかを見逃さないことが重要だと私は思います。
自分の目を引いたデザインだけに頼ると、必ず「なぜもっと冷却を考えなかったのか」と後悔する日が訪れるものです。
確かにファンの音は驚くほど抑えられましたが、その代わりにケース内部の熱が逃げ場を失い、夏場にはCPUの温度が危険域に達しました。
仕方なくフロントパネルを外してその場しのぎの通気を確保しましたが、正直とても不格好な姿で納得できるものではありませんでした。
静音性も冷却も両方中途半端になった体験は、私にとって「見た目や仕様説明だけで判断してはいけない」という大きな教訓になりました。
冷却性能を優先するのであれば、大口径の140mmファンをサポートするケースが間違いなく有利です。
小型ファンを数多く設置するよりも、大きなファンを低速回転で回した方が効率的で静かです。
これは私の経験則としても明らかで、高負荷時の安定感が全く違います。
さらに水冷クーラーの導入も有力な選択肢ですが、搭載スペースがなければ意味がありません。
実際、ケース内部の高さや奥行きが不足してしまえば、どれだけ性能の良い冷却機器を選んでも取り付けることすらできず、計画が完全に崩れます。
スペースの余裕こそが安心感を支えるのです。
展示会で見かけた木製フロントパネルのケースは、新鮮さと落ち着いた雰囲気でとても魅力的に映りました。
その質感に心を奪われましたが、奥行きやGPUとの相性を考えると実用性の面で迷いもありました。
インテリアとして部屋に馴染むか、それとも自分が本当に快適に使い続けられるか。
心が試されますよね。
例えば最新のCore Ultra 7 265Kを搭載するなら、まず優先すべきは確実な冷却性能です。
そのうえで、デザイン性とのバランスを加味するのが現実的な答えだと考えます。
特に長時間の配信やゲームプレイを続けるのであれば、安定した冷却環境が必要不可欠です。
ここを妥協して痛い目を見た人を、私は何人も見てきました。
GPUについても幅広い注意が求められます。
ケースの奥行きが410mm以上あれば安心ですし、十分な吸気と排気が設計されているケースなら、配信中の高負荷作業でも余裕を持って運用できます。
結局のところ重要なのは「余裕を残すこと」です。
このひと言に尽きますね。
最終的に私が強調したいのは、静音性を求めすぎて冷却を犠牲にしてはいけないということです。
大口径ファンとエアフローの設計があってこそ静音も生きるのであり、防音材だけに頼る選択は長続きしません。
そしてもう一つ、将来の拡張性を見据えてケースを選ぶことです。
GPUや水冷パーツの大型化は止まらないからこそ、余裕を考えて選んでおいたケースは長期的に安定した相棒になります。
最後に強く言いたいのはこれです。
ケース選びは単なる自己満足ではない。
毎日の快適さを根底から支える、大事な土台作りなんです。
Core Ultra7 265KゲーミングPCを組むときによく聞かれる疑問
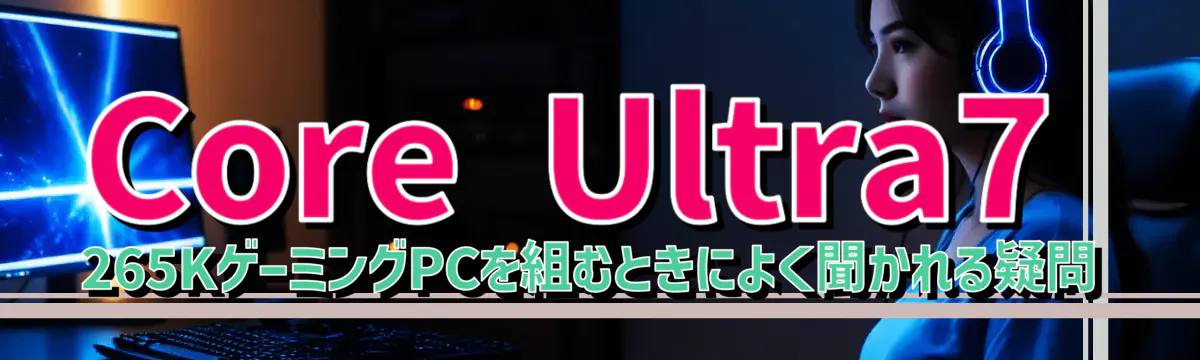
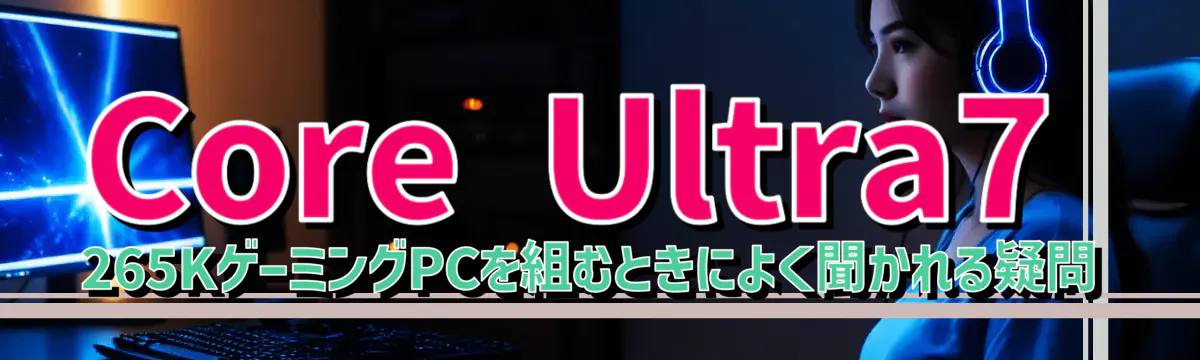
Core Ultra7 265Kは配信しながらゲームをこなせるのか?
以前はCPUやGPUの力不足が原因で、配信途中に映像が止まったり、音が途切れたりすることがあり、そのたびに視聴者に注意されるのが本当に嫌でした。
けれどもこのCPUに替えてからそうした不安が一気に消えたんです。
胸のつかえが取れたような感覚でした。
安心感って、こういうものなんだなとしみじみ思いました。
20コアという構成は、実際の使用感に直結していて、配信ソフトとゲームの処理をきれいに分担してくれます。
長年いろんなPCを触ってきましたが、配信しながらFPSをやっても画面がカクつかないというのは正直衝撃でした。
配信では一瞬のフレーム落ちで空気が途切れるものです。
その「空気を壊さない環境」を、このCPUはさらっと提供してくれる。
これは配信を続ける上でどれほどありがたいことか、同じ経験をした人ならわかると思います。
ただ、CPUだけで快適になるわけではないです。
冷却環境は本当に大事です。
私は空冷を選びましたが、サイズに余裕のあるクーラーを導入したので安心感があります。
長時間の配信でも静かで、しかもちゃんと冷えてくれる。
その結果、余計な雑音も気にならない。
水冷じゃなくてもやれるんだ、と改めて実感しました。
ただ正直に言うと、真夏の長時間配信では冷却が甘いと集中力が切れてしまいます。
これは身をもって知ったことです。
次にメモリです。
やっぱり32GBは必要だと感じました。
小さな不安定さも、ゲームの勝敗を左右する局面では致命的です。
私の場合はFPSをやることが多いので、その差はものすごく大きかった。
DDR5?5600のメモリに変えてからはフレームの乱れもほとんどなく、配信に集中できるようになり、今ではストレスを感じる時間がなくなりました。
精神的な安定に直結する部分ですね。
大容量の録画データを書き込んでも速度が落ちず、保存のたびに待たされる場面もありません。
正直、Gen.5も試しましたが数字のインパクトに比べて体感できる場面はかなり少ないものでした。
そのうえ発熱が気になる。
これなら価格と性能のバランス的にGen.4が最も実用的だと感じます。
使って納得する、そんな落としどころでした。
もちろん最初から確信を持っていたわけではありません。
Core Ultra9シリーズの方が長期的に見ればいいんじゃないかという気持ちもありました。
けれども実際に配信やゲームを回してみると、Core Ultra7 265Kで十分すぎるほどだったのです。
無理して上位を選ぶ必要はない、そう思えるようになった瞬間でした。
これがまたピタリと噛み合った感じです。
画質もスムーズさも思った以上に安定して、重いシーンでも焦らずプレイできる余裕が生まれました。
冷や冷やしながら遊ぶ必要がないというのは、精神的にとても大きいです。
この組み合わせなら、私自身あと数年は現役で戦えるなと手応えを感じています。
CPUとGPUの相性の良さは、机上では計算できない部分がありますが、試してみるとその差は歴然です。
昔は配信とゲームを同時に快適にやるなんて無理だと思っていました。
でもCore Ultra7 265Kでまとめた構成を試してからは、そうした不安が消えました。
安定して長時間配信できるというのは、自己満足ではなく、視聴者に迷惑をかけないという意味で大きな価値があります。
裏切られない安心感。
これは言葉にするとシンプルですが、実際の現場で得られる意味はまったく重みが違います。
最後に要点を整理すると、このCPUを軸に組むなら配信とゲームの両立は十分可能です。
条件は三つ。
メモリを32GBにすること。
ストレージを2TBのGen.4 SSDにすること。
そして冷却をきちんと整えること。
この三つをそろえれば、数時間の配信にも不安なく挑めます。
プレイに集中できる環境は、思っている以上に心を軽くしてくれるんです。
私はこのシステムを使ってから、本当にストレスが減り、ゲームや配信そのものを純粋に楽しめるようになりました。
快適さとコストの納得感、その二つがそろったのは久しぶりでした。
だからこそ、Core Ultra7 265Kを中心とした構成こそが、現時点で最も実用的で気持ちよく使えるベストバランスだと胸を張って言えるのです。
自信。
RTX5060Tiを使った場合に体感する最新ゲームの快適さ
以前は高画質に設定するとどうしても処理落ちにイライラさせられ、せっかくの楽しみが台無しになっていたのですが、今はまるで別世界。
AAA級のタイトルを最高画質で動かし、フルHDはもちろん、WQHDですら快適に遊べる。
この切り替えの瞬間に感じる余裕、その存在こそ投資の成果だと心から実感しました。
テクスチャを高設定にして、レイトレーシングまでオンにしてみたのですが、これは絶対重くなるだろうと半ば予想していたのです。
ところが予想を裏切って、戦闘シーンも一切カクつかず、むしろ映像美と滑らかさがきれいに両立していました。
正直、映像に入り込む感覚に浸れるというのはゲーム体験の本質だと思います。
高画質で遊べるだけならまだしも、私にとって大きな変化は配信でした。
趣味でゲーム実況をしているのですが、以前は正直なところ妥協だらけ。
配信とゲームを同時に動かすとどうしてもGPUに負荷がかかり、やむを得ず画質を落として対応していたのです。
それがこの構成にしてからは全く違います。
配信を同時にしても映像が乱れない。
CPUの20コアが余裕をもって処理を捌き、GPUはグラフィック描画に専念してくれる。
視聴者から「画質が安定して見やすい」とコメントをもらった時には、思わず笑ってしまいました。
そして想定していなかったのが静音性です。
RTX5060Tiの効率性のおかげなのか、長時間プレイしても熱がこもりにくく、ファンがやたらと回ることがない。
昔使っていた環境ではファンノイズが耳について仕方なく、深夜に遊ぶのが気が引けるほどでした。
でも今は違う。
静かで力強い。
そう表現するのが一番近いと思います。
もう音に気を散らされることはありません。
さらに反応速度。
この構成でシューターを試したときは驚きました。
Reflex 2のおかげで入力から画面への反映がぐっと速くなり、射撃のタイミングが手に吸い付くように決まる。
以前の重たい環境では考えられなかったことです。
正直、一度慣れてしまうと昔の環境には戻れません。
プレイそのものの楽しさが一段階引き上げられた、と強く感じました。
加えて感じるのが柔軟性です。
フルHDの余裕、WQHDの安定、さらに設定を工夫すれば4Kでも遊べる。
この守備範囲の広さは、ミドルレンジとしては破格だと私は思っています。
もちろん絶対的な性能でハイエンドに劣る部分はある。
しかし価格や消費電力とのバランスを考えた時に、あえてこのレンジを選ぶ価値が際立つのです。
万能感。
オープンワールド系の街に入った瞬間、人々や建物が滑らかに動いていて、以前は必ず起きていた処理落ちが一切見られない。
ああ、やっと来たか、とその時は小さくつぶやきました。
自分のお金を注ぎ込んだ意味が目の前で証明されたような感覚でしたね。
それからレイトレーシング対応タイトルでも試しました。
過去は設定を落とすのが当たり前で、快適さと映像美は天秤にかけるしかなかったのです。
しかし今はむしろ「どこまで上げても耐えられるのか」と試したくなる。
これは本当に新しい体験でした。
設定画面を開くときにワクワクするなんて、久しくなかったことです。
だから私はこの構成を「快適性とコストパフォーマンスを同時に狙える最適解」だと思っています。
配信を絡めたい人には特に勧めたい。
最新ゲームも配信も両方やりたい人にとって、このバランス感覚は心強い。
迷わせない。
私の正直な気持ちとして、この組み合わせにしたことでようやく「遊びたいように遊べる環境」を手に入れられたと思っています。
そして今後しばらくはこの環境で、胸を張って趣味を楽しみ尽くすつもりです。
こんなにも納得できる買い物をしたのは久しぶりです。
265K搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55EM


| 【ZEFT Z55EM スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | CoolerMaster COSMOS C700M |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (FSP製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55HS


| 【ZEFT Z55HS スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5080 (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54W


| 【ZEFT Z54W スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX3050 (VRAM:6GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G08FA


| 【EFFA G08FA スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54AP


| 【ZEFT Z54AP スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
配信PCにおける電源ユニットは実際どれくらいのW数が妥当か
配信用のPCを作るとき、私が一番強く意識しているのは「電源ユニットを甘く見ない」という点です。
正直に言って、ここを軽く考えると必ず痛い思いをすることになります。
CPUやGPUのパワーが上がるにつれて、必要な電力はとんでもない勢いで増えていくからです。
特に最近の高性能パーツを組み合わせた場合、スペック表の消費電力なんて当てにならない瞬間があります。
思わず跳ね上がる電力。
これに耐えられるかどうかで、配信の安定は決まるんです。
私はこれまで何度も自作をしてきましたが、650Wや750Wクラスで「まあ大丈夫だろう」と考えた時期もありました。
その時の後悔はいまでも忘れられません。
配信中に突然PCが落ちて、せっかく見に来てくれていた視聴者が一気に離れてしまった。
あの静まり返ったチャット欄の画面を見た瞬間、胸がぎゅっと締め付けられるような感覚に襲われました。
正直、ゲームが落ちるよりも配信自体が止まる方が何倍も辛い。
積み上げてきた空気が一瞬で消えるというのは、本当に心に堪えましたね。
今の世代を考えれば、850Wは最低ライン。
できれば1000Wを積む方が精神的にも安定します。
余裕のある構成の方が使用中に「大丈夫かな」と不安を抱えなくて済むからです。
機材に振り回されるのはもううんざりでした。
安心して座りたいんですよ、机の前に。
もちろん、選ぶGPUによって電源の必要容量は変わってきます。
たとえば消費を抑えたモデルを組むなら850Wで十分運用できるでしょう。
それでも一歩上のグレード、たとえばRTX5070Ti以上を導入するときは1000Wが必須になってきます。
「最近のパーツは効率が良くなってきたから少なめでも大丈夫だろう」と油断すると、いざというときに電源不足で落ちます。
配信とゲームを同時に負荷として掛けると、数字以上に消費が上がりますから。
そんな状態を750Wで回そうとすれば結果は火を見るより明らかです。
電源ユニットの選び方で、意外と見落とされがちなのが12Vラインの安定性と効率の部分です。
スペック表に書かれた数値だけ見て安心した気になるのは危険だと、私自身が体験しました。
昔、80PLUS Bronzeの電源を使っていたとき、夏場にファンがうるさくなり、配信中に視聴者から「後ろの音何?」と指摘を受けました。
その時は笑って流せましたが、配信は信頼商売です。
小さなノイズでも積み重なれば「この人の配信は不安定だ」と思われかねない。
悔しいけれど、それが現実です。
ですから、私は今では最低でも80PLUS Gold以上を選んでいます。
効率がよければ発熱も抑えられ、ファンの動作音も静かになります。
PCの内部で静かに仕事をこなしてくれることが、これほどまでに快適かと思わされました。
機械の安定は心の安定に直結する。
これは間違いありません。
さらに忘れてはならないのが、将来のアップグレードです。
最初は中堅クラスのGPUで十分だと思っても、新しい世代が登場すると気持ちが揺れてしまう。
新しく出たパーツにどうしても手を伸ばしてしまう。
私もその一人です。
そのときに「電源が足りないから全部やり直し」というのは愚かとしか言いようがない。
先を見据えて最初から1000Wを導入しておけば、未来の自分から「ありがとう」と言われます。
長い目で見れば結局そのほうがコストも下がります。
ここ数年の電源ユニットの進化には本当に驚かされます。
セミファンレス設計や日本製のコンデンサ搭載など、高品質な仕様がもう当たり前のようになってきました。
この技術のありがたみは、毎日長時間稼働させる人ほど感じるはずです。
私は長らくCorsair製を使っていましたが、最近試したDEEPCOOLの最新電源は衝撃的でした。
静けさと安定感が段違いで、「これはすごい」と思わず声が漏れてしまうほど。
家族に「何がそんなにすごいの?」と笑われましたけどね。
結局のところ、私が強く言いたいのはこれです。
配信者にとって一番大切なのは安定と信頼。
そしてその基盤を形作るのは電源ユニットなのです。
映像がどれだけ綺麗でも、マイクがどれだけ高音質でも、電源が脆弱なら一瞬で全て崩れ去ります。
体験済みだからこそ言えますが、本当に足元をすくわれるような感覚に襲われます。
だからこそ、Core Ultra7 265Kと高発熱のGPUを使うなら、850W以上を絶対に確保し、できれば1000Wを選ぶべきです。
この選択は安定した配信環境だけでなく、静音性や機材寿命にも深く関わります。
私はもう二度と妥協しません。
悔しい思いは十分にしました。
だから、迷っているなら声を大にして伝えたい。
これが配信者としての経験に基づいた私の答えです。
その二つが、長く配信を続けるための一番の武器だと私は思います。



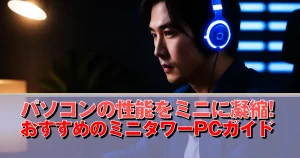
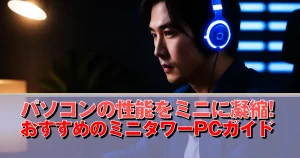
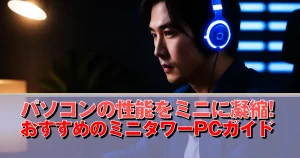



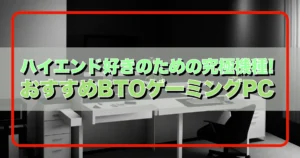
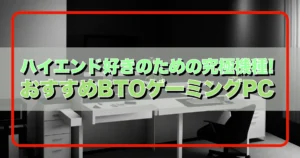
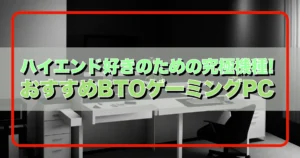
2TB超えのSSDは配信用途で本当に必要なのか
配信用にゲーミングPCを検討するとき、多くの人がまず気にするのはやはりストレージ容量です。
そして私がいろいろな経験からたどり着いた結論を先にお伝えすると、すべての人に2TBを超えるSSDが必要というわけではない、という点です。
ただし、配信のやり方や録画の扱い方、さらに編集まで視野に入れるかどうかで、その結論はガラリと変わってくるのも事実です。
たとえば、ただゲームを楽しみながら配信するだけの人であれば、正直1TBのSSDで十分足りるケースが少なくありません。
私自身、最新のタイトルをいくつもインストールして試してみましたが、それでも700GB前後に収まることが多く、1TBという枠は意外と余裕があります。
ただその余裕をどう使うかで、快適さは驚くほど変わるんですよね。
つまり一概に数字だけで決められないというわけです。
これが本当に厄介者で、私は高画質モードで数時間録画を続けたとき、予想以上の速さで数百GBが消えていく様子を目の当たりにして思わず「え、もうこんなに?」と声を上げました。
特に配信と編集を同じマシンでやる人間は、作業用の一時データ領域まで必要になってくるので、容量の確保が欠かせません。
私も配信の録画を全部残しておこうと欲張ってみた結果、2TBのSSDが一瞬で埋まり、渋々外付けドライブに逃げ込むはめになったんです。
あのときの狭苦しさといったら本当にうんざりでした。
では、最初から大容量の4TBモデルを選べばいいのかと言われたら、それもまた現実的ではありません。
確かに余裕は抜群ですが、お値段がとにかく張ります。
私はその出費を考えたとき「毎日高級ステーキを食べ続けるようなものだ」と思いました。
贅沢すぎて胃もたれしそうなんですよ。
だから私は今のところ、Gen.4の2TBモデルが一番バランスが取れていると考えています。
速度も十分速く、発熱も許容範囲、価格も比較的手を出しやすい。
このあたりが使い勝手の良い現実解でしょう。
それと忘れてはならないのが、録画用のストレージをシステムやゲームから分離するという考え方です。
これは強くおすすめします。
1TBをシステムとゲームの領域に、そして録画専用に2TB。
こうして分けてみたら、配信中のカクつきや挙動の不安定さがスッと消えて、驚くほど安定したんです。
やっと肩の荷が下りたような感覚でした。
役割をきちんと分けるのは、保険みたいなものなのだと痛感しました。
また、その録画をどう活用するかで容量の見積もりは大きく違ってきます。
単に配信を楽しむだけなら、録画データは必要なくプラットフォームのアーカイブに任せれば済む話です。
ただ、配信を編集してショート動画に仕立てたりSNSに載せたりするとなると、話は変わってきます。
私は仕事が一番忙しい時期にこの作業をやってしまったことがありました。
あのときの疲労感は二度と味わいたくないと今でも思っています。
未来の視点も無視できません。
映像業界や配信界隈は、確実に4Kや高ビットレートの時代に進んでいきます。
そのとき2TBなんて一瞬で埋まるんです。
保存した動画や素材は雪だるま式に増えていき、気づくと容量不足に振り回されることになる。
安心したいなら早めに手を打っておいた方がいい。
だから私ははっきり言います。
軽い配信だけを目的にしている人は2TBを超えるSSDは不要です。
しかし録画や編集を伴う本格的な配信を続けたい人は、2TBを超える余裕を持って構築するのがストレスをなくす一番の近道です。
私がおすすめするのはシステムとゲームが1TB、録画用に2TB以上という二枚体制。
この組み合わせなら配信も快適、編集も安心、保存も余裕。
三拍子揃った最適解です。
迷いますよね。
それができれば、SSDの選び方でつまづくことはなくなります。
1TB+2TB以上。
これ以上でもこれ以下でもない。
現実的であり、未来にも余裕を残す選択肢です。
最終的には人それぞれですが、一つだけ強調したいことがあります。
その性質を甘く見ないことです。
だから私は言います。
安心が違いますよ。
ストレージを選ぶことは、自分の未来への投資なんです。
初心者が構成を決める際につまずきやすいポイント
私がこれまで何台もPCを組んできて実感しているのは、高性能なパーツを単体で選ぶのではなく、用途や環境に即して全体のバランスを整えることが、最終的に一番満足できる形につながるということです。
豪華なCPUだけを突き刺したような構成では実際の快適さは約束されませんし、むしろ「せっかくお金をかけたのに、全然期待通りじゃない」と肩を落とすことになりかねないのです。
私の考えはシンプルで、投資すべきところと割り切るべきところを見極める冷静さが何より大事だという一点に尽きます。
かつて私はGPUを少し妥協したことがありました。
しかし実際に使ってみたら、プレイ中のフレームレートが不安定で、思わず唸ってしまいました。
「ああ、これじゃ没入感どころじゃないな」と思った瞬間の徒労感は今も忘れられません。
だからこそ断言できます。
ゲーミングPCにおいてGPUは心臓とも言える存在なのです。
ここを抑えるかどうかで体験の質が決まる。
だから私は常に「GPUこそケチるな」と声を大にして伝えています。
メモリもまた軽視しがちな領域ですが、これも侮れません。
カクつく画面に眉をひそめながら「やっぱり足りなかったか」と思うあの時間、正直イライラの連続でした。
結局32GBに増設したときに初めて、安心と余裕を感じられたのです。
余裕。
これは数字以上の価値を持ちます。
実作業に比例してストレスも減りました。
64GBまで積めばもっと安心できるでしょうが、現実的には32GBが境目と言えますね。
ストレージの重要性も忘れてはいけません。
私は最初Gen.4 SSDで十分満足していました。
起動も速いし、ゲームも快適だと思っていたのです。
しかし、Gen.5 SSDを試したときの衝撃は忘れられません。
しかも大容量データの展開も軽快で、「これはもう作業効率全体が変わるぞ」と感動してしまいました。
同じゲームなのに別世界にいるかのようなテンポ感でした。
冷却に関しても、軽視しては痛い目に遭います。
空冷クーラーでも一定の効果はあるのですが、長時間負荷をかけるとやはり限界がきます。
私は思い切って簡易水冷に変えたことがあったのですが、その瞬間から部屋全体の空気感が違いました。
音が静かになるだけでこんなにも集中できるのかと驚いた記憶があります。
「ああ、もっと早く導入しておけばよかった」と後悔したほどです。
安定性。
これが実際の体験を支える隠れた要素なのです。
過去に「デザインが格好いい」という理由だけで強化ガラスのモデルを選んだことがありましたが、結果的に内部の排熱処理が追いつかず、夏場は地獄のような熱気に悩まされました。
人に自慢できる見映えよりも、自分の生活環境にフィットする性能こそが最優先されるべきだったと痛感しました。
さらに私は電源不足で大きな失敗をしたことがあります。
PCは一応動作するのですが、あるとき突然シャットダウンして冷や汗をかいたのです。
原因が電源とは気づかず、しばらく右往左往して夜中に青ざめつづけた記憶は苦いものです。
それ以来、各パーツの消費電力と電源容量を意識して設計するようになりました。
互換性や余裕を考えないで突貫で組むと、必ず後でツケを払うことになる。
これだけは身をもって知りました。
では、どんな構成が理想か。
私の提案は明快です。
Core Ultra7 265Kを中心にするなら、GPUはミドルハイ以上、例えば最新世代の安心して長く使えるモデルを選ぶべきです。
メモリは32GBを最低ラインとし、SSDはGen.4以上で2TB以上を確保すること。
さらに熱対策に十分なケースと冷却システムを組み合わせ、電源にもしっかり余裕を持たせる。
これが安全策であり、使っていて不安を抱えない組み合わせなのです。
だから私は今も、この組み合わせを推します。
大切なのは数字の高さに酔わされないことです。
毎日の用途を意識し、自分に本当に必要なものを基準に選択すること。
それが「後悔しない選び方」につながります。
PCは単なる性能の集合体ではなく、日常の道具です。
机に向かうたびに「選んでよかった」と思える構成こそが最終的なゴールなのです。
そして最後に声を大にして伝えたいのは、失敗しても取り返しはつくということです。
ただ、その失敗を回避できるならそれに越したことはありません。
私は遠回りを経て学びました。
笑顔で電源を入れられる未来を。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |