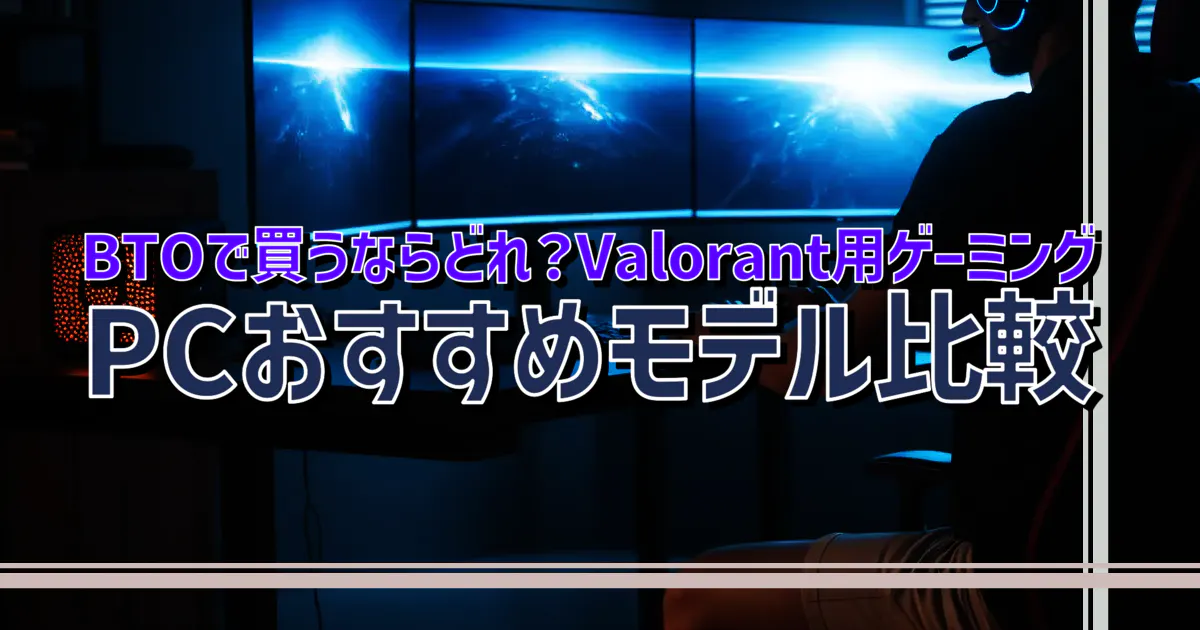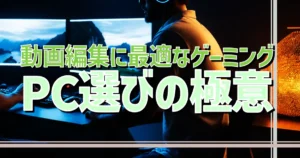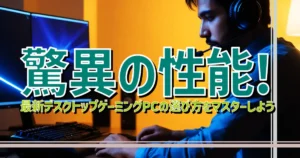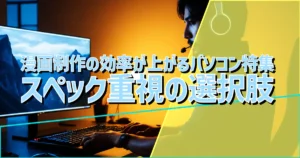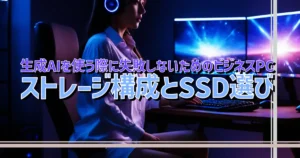Valorantをしっかり快適に遊ぶためのPCスペックまとめ

CPUはIntel派?Ryzen派?選び方のポイント
ゲーミングPCを選ぶときに避けては通れないのが、CPUをIntelにするかRyzenにするかというテーマです。
表面的には単純に見えるかもしれませんが、実際には自分がどんなプレイスタイルで、どんな環境を求めているのかによって最適解は変わってきます。
だからこそシンプルに割り切れる問題ではなく、むしろ悩む価値のある選択だと私は思っています。
長年PCを触り続けてきた私でも、この話題になるとつい熱が入ってしまうんです。
私の実体験で言えば、IntelのCPUはフルHD・240fps付近の環境で非常に力を発揮しました。
特にクロックの高さと単コア性能が効いているのか、Valorantの動きが明らかに滑らかになる瞬間を体感したことがあります。
あるときCore Ultra 7に切り替えたのですが、GPUは据え置きにもかかわらずフレームレートがぐっと上がった。
正直「ここまで違うのか」と、驚きと同時にちょっとした感動すら覚えました。
数字以上にプレイ中の手触りが変わるのが面白いんですよね。
これは一度味わうと忘れられない感覚です。
一方でRyzenには異なる魅力があります。
Ryzen 7 9800X3Dを試したときはキャッシュの恩恵が存分に感じられて、射撃や移動の動作が全体的に安定する印象でした。
実際の数値よりも「プレイヤー自身が安心できる」という価値を強く感じましたね。
あのときは「これはもう手放せないな」と、心から思ったほどです。
最終的な選び方は、自分がどの解像度やリフレッシュレートを重視するかで変わります。
フルHDで240Hzを安定させたいならIntelが最適と感じますし、WQHDやそれ以上の解像度で映像の綺麗さと安定を両立したいならRyzenが力を発揮する。
4K以上ではGPUがメインになるものの、それでもRyzenのキャッシュによる粘りの強さが光る場面はあります。
私は実際に、出張先ではIntel、自宅ではRyzenという形で両方を比較したことがあります。
フルHD低設定ではIntelの速さが際立ち、逆にWQHDではRyzenの落ち着きが勝る。
まるで野球でパワーピッチャーを出すか技巧派を信じるか、そんな議論をしているような面白さがあるんです。
どちらも捨てがたい。
また、値段の問題も非常に重要です。
BTOショップで見積もりを取ったとき、Intel構成はやや割高であるのに対し、Ryzenは同じ予算内でGPUをグレードアップしたり、追加メモリに回せたりするケースが多い。
私の印象では、学生や若手クリエイターはRyzen構成でコストパフォーマンスを追求しがちですし、大会を目指す若手プレイヤーはIntelを選びがちです。
それぞれの状況や目的によって自然と選択が分かれるのは面白いものです。
これを軽視すると後悔しか残りません。
私は過去に電源を安物で済ませた結果、大事な試合中に強制再起動を食らったことがあります。
あの瞬間の悔しさは今思い出しても胃が痛くなるほどです。
それ以来、私はCPUクーラーと電源は迷ったら上位モデルを選ぶように決めています。
数千円を惜しんだ代償は、本当に大きいんです。
だからこそ声を大にして言いたい。
ここで妥協するな、と。
つまりまとめると、フルHDで高リフレッシュレートに張り付きたいなら私はIntelをおすすめしますし、解像度が高めで映像の美しさを求めつつ安定感も重視したい方にはRyzenのキャッシュ搭載型CPUが噛み合います。
実際に両方を使ってみて、どちらにも明確な価値があることを身をもって知りました。
優劣の問題ではなく、プレイヤーが「自分の試合でどんな戦い方をするのか」という目線で答えが決まる。
これこそが一番大事な視点です。
綺麗事を抜きに言えば、このCPU選びを脇役にしてはいけません。
BTOでパソコンを組むとき「とりあえず残った方を選ぶ」なんて消去法的な決め方では絶対にもったいないです。
Valorantのように一瞬の判断が勝敗を分けるゲームだからこそ、自分のプレイスタイルに正面から向き合って、その感覚に合う方を選ぶ。
それが結局、後悔しないための最短ルートなんです。
この考えに辿り着くまで私は何度もPCを買い替え、試行錯誤を繰り返してきました。
財布は痛みましたよ。
本当に。
でもその過程で「自分にとって快適とは何か」という一本の軸を見つけられた。
だから今でもIntel機とRyzen機を手放せず、両方を手元に置いています。
気づけば生活の一部。
いや、仕事や遊びに欠かせない相棒です。
安心できる環境。
それが、最終的に私を支えてくれるものだと心から思います。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43031 | 2479 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42785 | 2281 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41817 | 2272 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41110 | 2371 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38579 | 2090 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38503 | 2060 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37270 | 2369 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37270 | 2369 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35641 | 2210 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35500 | 2247 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33752 | 2221 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32894 | 2250 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32526 | 2114 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32416 | 2206 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29247 | 2051 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28533 | 2168 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28533 | 2168 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25444 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25444 | 2187 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23080 | 2225 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23068 | 2104 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20850 | 1870 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19500 | 1948 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17726 | 1826 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16041 | 1788 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15284 | 1993 | 公式 | 価格 |
グラボはどのランクなら安心して快適に遊べる?
多少妥協してお金を節約した結果、後から不満が募って買い直す羽目になるのなら、最初から必要十分なものを選ぶのが結局一番コストがかからない。
私自身、実際にそういう経験をしてきました。
だから言えるのです。
妥協は後悔を呼ぶだけだと。
Valorantというゲームは、他の重たいAAAタイトルと比べると必要スペックは確かに軽めの部類に入ります。
普通にプレイするだけなら、そこまで高性能なGPUを要求されるわけではありません。
しかし問題はそこから先です。
競技として真剣に取り組むなら、240Hz以上のリフレッシュレートでプレイできる環境こそが標準。
私が最初に導入したのはミドルクラスの5060Tiでした。
フルHD環境でプレイする分には大きな不満もなく、低中設定なら安定して動作していました。
ところが解像度をWQHDに切り替えた時、状況は一変しました。
煙が展開された瞬間にfpsが160程度まで落ち込み、細かい入力遅延が妙に指先へ伝わってプレイ感覚が重くなる。
画面の一瞬の引っかかりが致命傷に繋がるゲームでこの違和感はキツい、と素直にそう感じたのです。
その時「これは無理だ」と確信しました。
あれほど気になっていたカクつきや遅延が嘘のように消え、同じゲームなのにここまで体験が違うのかと驚愕しました。
戻れない感覚というのは、まさにこのことです。
FPSを本気でやる人にとって、ほんの少しの入力遅延やフレーム落ちが勝負を分けることがあります。
その意味で「他のパーツを削ってでもGPUは優先する」という考え方は正しい。
CPUやメモリももちろん重要ですが、グラフィックカードだけは絶対に妥協できない基盤です。
性能不足のGPUを選んでしまえば、後からどれだけ他を補強しても根本の不満は消えません。
最近ではFSRやDLSSといったフレーム補完技術が進歩しています。
例えば射撃時に背景が微妙に歪んだり、キャラクターの動きがわずかにねっとりと感じられたりする。
普通に遊んでいるときには気にならなくても、集中すればするほど「なんだこれは?」と目についてしまうのです。
その瞬間、ゲームに没頭していたはずの意識が崩れてしまい、パフォーマンスを落としかねません。
違和感はストレス。
昔、同僚のアドバイスで「これで十分だろう」と言われてミドルレンジGPUを購入したことがあります。
でもしばらくして大会配信を見た時、自分の環境との差を痛感しました。
チームメイトより明らかに反応が遅れ、「これって自分の腕のせいじゃなくて機材の影響もあるのでは?」と疑い始めた。
正直、その時の悔しさは忘れられません。
最終的にグレードを上げて買い直したとき、そこで初めて本当の快適さを知りました。
だから私が強調したいのは、GPUのグレードを「最低限動けばいい」という基準で選んではいけない、ということです。
フルHDで240fpsを安定させたいなら5060Ti、WQHD144Hz以上を出したいなら5070かRX9070XT、それに4K解像度できれいな映像を求めるなら5080やそれ以上といった具合に、用途に合わせて必要十分な選択をすべきなのです。
安くない買い物だからこそ、最初に中途半端な選択をすると「なんであの時ケチったんだ」と確実に後悔する。
それが嫌なら潔く初めから投資するべきだと、過去の私は身をもって学びました。
快適さは勝敗を左右する環境において、たとえわずかであってもフレーム落ちを許さない。
そのこだわりが結果に直結します。
動作が安定し、遅延を感じない環境があれば、プレイヤーは余計なことで集中を乱されずにプレイそのものに没頭できる。
GPUを選ぶというのは、単なる買い物ではなく、自分がどこまで本気でゲームに向き合うかの覚悟でもあるのです。
安心感がある。
結局のところ、私がこれまでに学んできたのは「安さに負けて中途半端に選んではいけない」という一点に尽きます。
結果的に買い直すより、余裕を持って性能の高いものを最初に選んだ方が、時間もお金も精神的な負担も少ない。
後悔した自分の過去を思い返すと、なんであの時に素直に自分が欲しいものを選ばなかったのかと情けなくなるほどです。
これから選ぶ方には、同じ轍を踏まないでほしい。
自分が心から納得できる環境を整えることが、長くゲームを愛し続けるための最良の投資になります。
それは単に快適だから、ということにとどまらず、毎日プレイするたびに「ああ、選んで正解だった」と思える満足感へつながっていくのです。
長い目で見れば、余計な遠回りをせずに済むのは間違いありません。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48655 | 102452 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32127 | 78469 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30130 | 67099 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30053 | 73798 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27143 | 69279 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26486 | 60545 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21934 | 57089 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19905 | 50739 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16548 | 39572 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15982 | 38394 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15845 | 38170 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14628 | 35097 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13733 | 31016 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13193 | 32525 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10814 | 31904 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10643 | 28730 | 115W | 公式 | 価格 |
メモリは16GBで足りるのか、それとも32GBに投資するべきか
私が率直に伝えたいのは、Valorantをプレイするだけであれば16GBのメモリでなんとかなります。
ただし「今は問題ない」と思える状況でも、いずれ窮屈さを感じる時が来る、ということを実感しているのです。
実際に私がフルHD・240Hzの環境で試したときには、不満を抱くような場面はほとんどなく、使用量も10GB程度に収まっていました。
しかし、その時の気分は「とりあえずは問題ない」という小さな安心感に過ぎず、どこか心許なさが残っていたのを覚えています。
私が改めて考えるきっかけになったのは、ゲームをしながらDiscordで通話し、さらにはOBSを立ち上げて配信を行った時でした。
画面を切り替えるたびに、わずかな遅延と反応の鈍さが積み重なってストレスに変わり、集中が乱れてしまったのです。
プレイそのものは成立していても、気持ちが揺らぐと結果的にゲームの質が落ちる。
これを何度か体験したことで、私は自分の中で「やっぱりメモリを増やさなければ」という強い意識に変わりました。
その後、思い切って32GBに増設した瞬間から、環境が一変しました。
複数のアプリを並行して動かしても不安感が存在しなくなり、モニターを見つめる自分の心境が落ち着いたまま保てるのです。
やっぱりこれだ、と心の底からホッとしました。
こうした安定感は、自分で体験してみないと分からないものですね。
16GBとの差が数千円から1万円程度なら、長く安心して使える32GBを選んだ方が結局は得策だろうと実感しました。
私は「後悔したくない」という自分の気持ちを優先し、少し無理をしてでもそちらを買いました。
ですが、ゲームはアップデートによって急に要求スペックが上がることがある。
その時に余裕を持っておくのは、自分自身への未来の投資であると強く感じています。
複数のアプリを立ち上げても余裕がある。
配信も録画も不安なくこなせる。
メモリ残量を心配せずに済む環境が、どれだけ精神的な余裕を与えてくれるか――これは経験しないと伝わりにくいでしょう。
私はこの余裕があるからこそ、プレイ中に集中を切らさずにいられるようになったのです。
さらに業界全体の流れを知ると、この安心感はますます重要に思えてきます。
最近ではAAAタイトルの多くが32GBを推奨し始めています。
Valorantは軽めの部類に入るとはいえ、ゲーム業界全体を見れば「16GBではそろそろ物足りないのでは」という声が広がりつつあります。
実際、かつて軽快だったゲームもアップデートを重ねてどんどん重くなるケースは多い。
だからこそ、いまから備えておくことで将来への不安を取り除けるのだと思うのです。
私はもう16GBに戻すつもりはありません。
余裕のある構成は作業環境もゲームも安定させてくれるだけでなく、精神的にも余裕を生んでくれるからです。
だからこそ、これからパソコンを購入する人、あるいは買い替えを検討している人には強く伝えたい。
私は32GBにしてから、本当に気持ちが変わりました。
起動も切り替えもスムーズになり、試合に集中できる時間が圧倒的に増えました。
ちょっとした遅延で苛立つこともほとんどなくなり、心の持ちように余裕が生まれたのです。
正直、この効果はお金の差をはるかに上回っていました。
最終的にはシンプルな話です。
Valorantを快適に遊ぶだけなら16GBで済む。
けれど、配信や録画を行い、複数のアプリを動かす可能性があるなら32GBを選ぶべき。
快適さ以上に、安心につながるからです。
迷って考え込む時間が一番もったいない。
だから私は、一歩踏み出す選択をしたのです。
安心できる環境。
SSDは最低どれくらい積んでおけば困らない?
500GBでもなんとかなると思い込んでいた時期がありましたが、それは大きな間違いでした。
実際のところ、ゲームや業務アプリ、そして日常的なデータ保存を考えれば、500GBでは息苦しいのです。
昔の私は軽く見積もっていました。
「当面は大丈夫だろう」と。
でも現実は残酷でした。
大事に残しておいた録画データを泣く泣く削除する羽目になった時、心の中で「いったい何をやってるんだ」と自分に突っ込みました。
楽しみのはずのゲームが、ストレージ不足のせいでストレス源へ変わってしまったんです。
その時の悔しさは今でも鮮明です。
だからこそ、これからゲーミングPCを選ぶ人にははっきり伝えたい。
500GBはやめておいた方がいい、と。
今のゲームは数十GB単位のアップデートも珍しくなく、作り込みもどんどん重厚化していてデータサイズは膨らむ一方です。
しかもOSや仕事用アプリも同じドライブに入れるのですから、ゲームを楽しむどころか容量不足の管理に追われる毎日がやってきます。
そんな苦境にわざわざ飛び込む意味はないでしょう。
それに比べて1TBの余裕は大きいです。
何より心の安心感が違う。
空き容量を気にせずインストールボタンを押せる快感。
新しいタイトルを即座に試せる自由。
仕事の資料や動画ファイルも、削除に神経を使うことなく置いておけます。
私は「余裕のあるストレージは精神的な安定剤だ」と実感しています。
Gen.5は確かに速いけれど、発熱対策や値段の高さに振り回されては本末転倒です。
余計な気苦労を抱えず済む構成こそ長く快適に使えるのです。
では2TBはどうなのか。
私は仕事でもPCを使うため、業務データと大型ゲームを共存させたいという欲張りな状況でした。
だから思い切って2TBを選びましたが、この決断は正解でした。
いざ蓋を開けてみると、どんなファイルも安心して保存できる自由は想像以上に大きく、「あれもこれも残しておける」という余裕が生活の快適さを数段引き上げてくれました。
お金で買えるのは容量だけではなく、心の余裕そのものだったのだと気づきました。
逆にプレイ本数を少なくできる人なら1TBでも十分使えるでしょう。
ただ、それを前提にしても、やはり余裕の投資は後から効いてくるのです。
業界全体のソフトがどんどん大容量になっていく中で、余裕を持った選択は最終的に出費も手間も抑えます。
途中で増設しようとすればコストも時間も二重にかかり、さらにトラブル対応にまで追われることになりかねません。
それなら最初から容量の広いドライブを搭載する方が、どれだけ効率的で精神的にも救われるか。
私はそこを強調したいです。
500GBの落とし穴には本当に注意すべきです。
安さに引かれてつい選びそうになるかもしれませんが、半年も経たずに「やっぱり失敗した」と後悔する人を何度も見ています。
私もその一人でした。
せっかく新しいPCを買ったのに、ワクワクした気持ちよりも空き容量との戦いの方が先に思い出されてしまう。
だから大きな声で言いたいんです。
「500GBはやめておけ」と。
特にSSDは快適さに直結する部品です。
ロード時間の短縮はもとより、動作全体の滑らかさや作業効率にも関わります。
ここで妥協すれば、毎日の体験が目に見えて劣化します。
私ならマウスやキーボードを多少グレードダウンしてでも、ストレージ容量は絶対に優先します。
快適さを決定づける要素だからです。
だから結論はシンプルです。
ゲーミングPCを買うなら、最低1TB。
余裕を強く求めるなら2TB。
それが現実的で失敗しない選び方です。
ストレージをケチっては本来の楽しみや効率を奪われてしまう。
最初の段階でたっぷり積んでおけば、それだけで毎日のストレスはぐっと減り、安心して仕事にも遊びにも打ち込めます。
容量の余裕は、心の余裕。
そしてそれが一番の投資効果だと私は信じています。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
コスパを重視したValorant用ゲーミングPC構成例
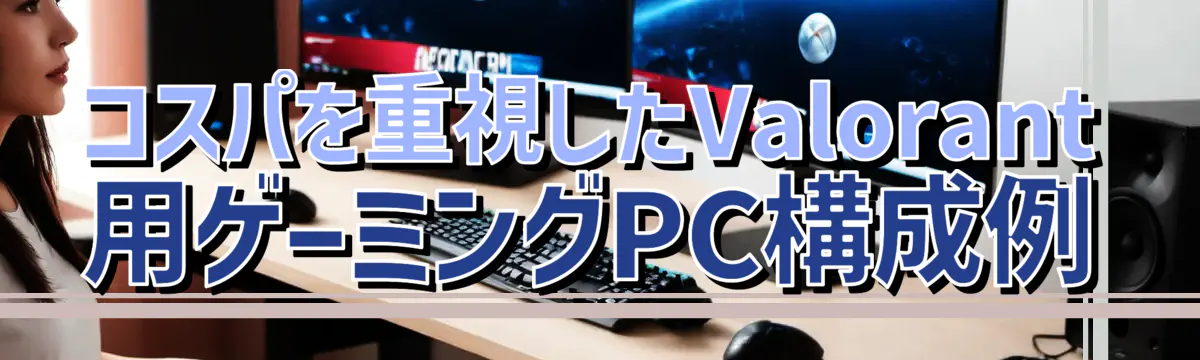
予算10万円台で狙えるRTX搭載モデルの実例
冷静に比べていくと、まずはRTX 5060TiとCore Ultra 5を組み合わせたモデルが価格と性能のバランスで頭一つ抜けています。
そしてもし3万円から5万円ほど余裕を出せるのであれば、RTX 5070とCore Ultra 7の組み合わせへ投資しておくことが、後悔のない選択になるはずです。
10万円台半ばという価格帯は、現実と夢の間で折り合いをつけるちょうどよい領域です。
最新のValorantを240fps以上で動かせる力がありながら、コストが跳ね上がりすぎるわけではない。
この絶妙なバランスにこそ「選びやすさ」を実感しました。
実際、私は息子から「一緒にFPSをやろう」と誘われて機材を探し始めたのですが、その時に初めて、このクラスのBTOこそが予算と実用性を自然に両立してくれるポジションなのだと納得させられました。
例えばCore Ultra 5 235FとRTX 5060Tiの組み合わせは、見た目のスペック以上に好印象です。
フルHD環境で試したとき、200fpsを軽々と超えたうえにフレーム落ちがほぼなく、画面が揺れるような不快感もありませんでした。
その滑らかな映像を見て、私は思わず肩の力が抜けたんです。
なぜなら、もし画面が頻繁に引っかかれば集中力も消えてしまい、せっかくの時間がすぐストレスに変わってしまうからです。
安心感って本当に大事なんです。
もしワンランク上を求めるならCore Ultra 7 265KとRTX 5070が選択肢に浮上します。
価格は10万円台後半に突入するので躊躇はありますが、WQHD環境で遊ぶのであればこの上積みの価値は明確です。
特にUnreal Engine 5が当たり前に採用され、ちょっとした映像表現が一気に負荷へと跳ね上がる。
そんな流れを見ていると、先を見越した投資が結果的に安心につながることを痛感します。
性能面だけでなく、使いやすさで驚かされたのが静音性です。
冷却ファンの回転音が想像を超えるほど抑えられていて、つい「おお、静かだな」と声が出ました。
正直、数時間以上のプレイ中に耳へ響くノイズは思っている以上に疲れを溜めます。
その点でケース内部のエアフローを含めた設計が良ければ、プレイ体験は格段に快適になるのです。
音が静か。
それだけで気分が違うんです。
加えて、このクラスのBTOは標準で16GBのDDR5を備えていることが多いです。
DDR5-5600なら動画を流しながらのゲームプレイも余裕ですし、大体の場合1TBのGen4 SSDが搭載されています。
ロードの速さは桁違いで、ゲーム選択から実際のプレイに入るまでの時間が驚くほど短縮されます。
一度この快適さに慣れてしまうと、もう古いHDD環境には戻れません。
数秒の遅延でもイライラするんですから。
だからこそ、ここで妥協するのは失敗だと私は思います。
一方で、意外と見落とされやすいのが電源ユニットです。
ここを軽視すると後で痛い目を見ます。
GPUを交換したいと思っても必要なワット数が足りない、あるいは効率が悪く動作不安定に陥る、そんな事態は珍しくありません。
最低650W、できれば80PLUS Goldあたりを意識しておくべきです。
電源に手を抜かないこと。
これが機械全体の信頼性を決めます。
少し前に知人のBTO選びを手伝ったのですが、まさにここで勉強させられました。
RTX 5060Tiと5070の間の価格差はおおよそ1万円少々。
その違いは単なるスペック表の数値以上のもので、安心感や快適さを買う1万円が意外なほど大きな意味を持つのだと、彼と一緒に納得するしかありませんでした。
もちろん見栄を張って上の構成を選ぶ必要はありません。
ただ、譲ってはいけない部分は確かに存在します。
私の経験上、5年から6年と長く付き合うつもりなら、やはり5070搭載のモデルを選んでおく方が後悔は少ないでしょう。
ただし「今すぐ快適に遊べればいい」と割り切れるのであれば、5060Tiでも何の問題もありません。
自分が何に重きを置きたいか。
それだけです。
最終的に10万円台の予算でValorantを楽しみたいなら、実際の選択肢は二つに絞られます。
手堅く行くなら5060TiとCore Ultra 5、余裕を見込むなら5070とCore Ultra 7。
悩んで遠回りしても結局この二択に戻ってくるんです。
選んでよかった、と。
配信も考えるならRyzen 7+32GBメモリという選択肢
配信を考えるなら、私はRyzen 7と32GBメモリを強く勧めます。
これは単なる数値上の話ではなく、実際に体験して痛感した「安心して長時間配信を続けられるための最低限の投資」だからです。
ゲームだけを遊ぶのであれば16GBでも不満は小さいですが、配信やマルチタスクを本気でやろうとすると、その差がはっきりと表に出てしまいます。
私は16GBの環境から32GBへ切り替えた瞬間、まるで別世界になったかのような軽快さを味わいました。
その時、心の中で「これでやっと余計なイライラから解放される」と叫んでしまったのです。
思い返すと16GBの頃は、ちょっとしたラグやコマ落ち程度でした。
しかし長時間になるにつれ、それがじわじわと私自身の集中力を蝕んできました。
あるとき自分が「今ちょっと重かったね」と言い訳するように口走っていることに気づいた時、もう心から楽しめていない自分がいたのです。
だからこそ、Ryzen 7の余裕あるマルチスレッド性能と32GBのメモリは欠かせないのです。
OBSを立ち上げながら複数のブラウザタブを開き、チャットも通知アプリも同時に動かしたとき、16GBではどうしても窮屈さを感じました。
けれど32GBにした瞬間、切り替えのレスポンスは驚くほどスムーズになり、エンコード中に別の作業へ移っても問題がほとんど起こらない。
小さな快適さの積み重ねが、大きな安心感につながるのだと強く感じました。
しかも最近のValorantはUnreal Engine 5へ移行してから、背景の光表現やエフェクトが以前よりはっきりと負荷をかけるようになったと実感しています。
GPUの負担が大きい場面ではCPUやメモリの余力が不可欠で、そこを惜しむとすぐに映像や操作の乱れとなって現れるのです。
だからこそ、今から安心できる投資をしておく。
それは未来に対する備えであり、自分自身を守る行動です。
過去に私はGPUを軽視したことで後悔した経験があります。
ゲーム自体は快適に動きましたが、配信映像にはどうしてもわずかなもたつきが出てしまった。
最終的にグラフィックボードを買い直すはめになり、余計な出費となりました。
この経験から「CPUとメモリだけに偏った構成は危険だ」と強く刻み込みました。
やはりバランスこそ正解です。
もしWQHD以上の解像度で配信を考えるなら、RTX 5070クラスを目安に選んでおくと安心です。
人は後で買い替えると「最初からそうすればよかった」と悔やむ。
私もそうでした。
最初から覚悟を決めた方が絶対にストレスが少ないのです。
次に忘れてはいけないのがストレージです。
配信者にとって録画ファイルは予想以上に容量を食います。
SSDは最低でも1TB、できればもっと欲しいくらいです。
収録中に「容量が足りない」と焦る瞬間ほど嫌なものはありません。
そうなると作業リズムが崩れ、配信そのものの魅力まで削がれます。
正直、カクつきと容量不足、この二つは致命的です。
つまり大事なのは最初の決断で迷わないことです。
Ryzen 7と32GBメモリ、きちんとしたGPU、そして十分なSSD。
これを揃えておけば大失敗は避けられます。
私はそれを自分の失敗と経験から断言します。
ここで一つ短く言います。
安定感は努力の価値を裏切らない。
そして最後に強調したいのは、配信の世界では「安定」を欠くと一瞬でリスナーが離れてしまうということです。
それは自分自身の気持ちが萎える瞬間でもあります。
せっかく自分も楽しもうと用意した時間が無駄になってしまう。
そんなのはもったいないにもほどがありますよね。
だから私は迷わず「安定した配信が続けられる未来」を選びたい。
結局そこに行き着くのです。
もし本気で配信を続けたいなら、余裕を持った環境を整えるべきです。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55XC

| 【ZEFT Z55XC スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R66M

| 【ZEFT R66M スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH170 PLUS Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58V

| 【ZEFT Z58V スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | LianLi A3-mATX-WD Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R63V

| 【ZEFT R63V スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster MasterFrame 600 Black |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R58DG

| 【ZEFT R58DG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
ストレージ容量を工夫して予算を抑えるアイデア
今はむしろ、最初は最低限で揃えてあとから足す。
そのほうが明らかに肩の力が抜けます。
例えばValorantを中心に遊ぶなら1TB程度のSSDで実用的に十分なんです。
私が使っているサブ機もそれくらいですが、不便に思ったことはまずありませんでした。
これ、本当にあるあるです。
実際のポイントは「ストレージは必要なときに増設できる」ことです。
最初から2TBや4TBといった高容量を選ぶより、まずは価格のバランスがいい1TBのNVMe Gen4 SSDを使えば十分です。
SSDの相場はどんどん下がっていくので、焦って買うとすぐに「あのとき待てばよかった」と悔しくなるんです。
だから必要になってから買う。
シンプルだけど、それが一番ラクで堅実な姿勢なんだと、何度も組み替えてきた今の私には強く実感できています。
そう、後から間に合うんです。
ただし容量よりも速度は絶対に譲れません。
価格の安さでHDDを選んでしまうと起動やロードで待たされるストレスがどんどん積み上がります。
ゲームをやるならSSD一択。
さらにいえばGen4がベストバランス。
最新のGen5 SSDも試したことがありますが値段が跳ね上がるわりにゲームの起動体感はGen4と変わらない。
しかも発熱が強くて冷却を別途考える羽目になる。
正直に言えば「見せる性能」であって、生活の中ではオーバースペックに感じました。
大変だったのはゲーム自体ではなく録画データです。
配信や保存をしていると、数時間分の動画が一気に容量を食い尽くしてしまいます。
私も一度、システムと録画データを同じSSDに置いてしまい、残り容量がカツカツになったことで作業全体が重くなり、本気で焦った経験があります。
そのときに救われたのが外付けSSDでした。
USB4やThunderboltで接続できるモデルなら転送も高速で、録画を気にせずどんどん保存できる。
メインは軽々、録画は安心。
この分け方は、今振り返ってもかなり賢い方法だと断言できます。
またBTOパソコンを選ぶときに「追加ストレージ」に惹かれる人も多いと思いますが、私はあまりおすすめしない立場です。
昔、BTOのオプションで2TB SSDを選んでしまったのですが、今思えば本当に割高でした。
後から自分で市販のSSDを買い増ししたほうが断然安くて性能も高い。
届いたPCをすぐ使える便利さは魅力的ですが、冷静に見れば損のほうが大きかったなと悔しさが残りました。
その経験があるからこそ、今は「自分で後から足す」ことを推したい気持ちがありますね。
クラウドの利用も現実的な選択肢です。
ただ、ゲーム本体まではクラウドに置けないので、基本はSSDを用意し、クラウドは補助と割り切るのが一番自然だと考えています。
私がようやく落ち着いた形は、シンプルに1TBのNVMe Gen4 SSDを中心に構成し、必要が出てきたら外付けや増設をプラスしていくスタイルです。
録画や動画保存は別のドライブに逃がし、メインを軽く保つ。
ゲームを遊ぶ上での快適さというのは単なる数値以上に「気持ちの軽さ」が重要なんだと、私はこの歳になってしみじみ思うんです。
なによりもPCとの付き合いは長期戦です。
若い頃はとにかく最新スペックや容量の多さに手を伸ばし、「最高の構成にした!」と満足していましたが、結局は余らせたり使いこなせなかったりして後悔することがほとんどでした。
ところが40代になって、生活や趣味との折り合いを考えるようになってから「結局は何が本当に必要なのか」がようやく見えてきました。
冷静さ。
この二つを守ることで得られる手応えは性能の数値よりはるかに価値があると思います。
ぜひこれからゲーミングPCを考える人には、「ストレージは後から増やしてもいい」という感覚をもってほしいです。
そのゆとりさえあれば、満足度の高い一台と長く付き合えるはずですよ。
高fpsを狙ってプレイする人のためのValorant PC選び
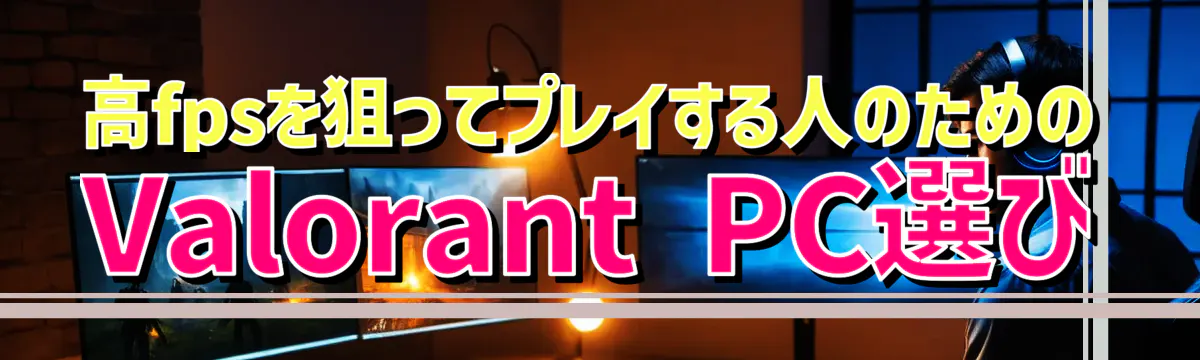
144Hzや240Hzを活かすために必要なGPUの実力
高リフレッシュレートのモニターを本当に活かすには、GPUの選択を誤らないことが何よりの肝だと私は強く感じています。
良いモニターを手に入れたところで、裏方を支えるGPUが力不足では結局そのメリットを享受できない。
この事実は、実際に何度も体験してようやく骨身にしみました。
以前、私は240Hz対応のモニターを導入しました。
ほんの一瞬のラグやドロップでさえ、心のどこかに苛立ちが走り、集中の糸がぷつりと切れる。
あの感覚は忘れられないですね。
想像以上に精神へダメージが来るんですよ。
経験を通して学んだのは、144Hzあたりなら最新世代のミドルレンジGPUでもなんとかなるが、240Hzを安定的に出すとなるとやはり話が変わるということです。
Valorantは一見軽いタイトルに見えますが、一斉にスキルが飛び交うシーンなどでは負荷が跳ね上がる。
気を抜いてミドルレンジを選ぶと「思ったより出ないじゃないか」と必ず悩む羽目になる。
これは痛い思いをする前に知っておくべき真実です。
その話を聞いたとき、私はやっぱりそうかと納得しました。
競技レベルで取り組むなら、RX 9070以上を意識するしかない。
GPU性能の「余裕」とは単なるスペック表の数値ではなく、プレイする本人の心の落ち着きを守る力にもなるんですよね。
一般的な社会人ゲーマーが144Hz狙いであれば、RTX 5060 Ti や RX 9060 XTは良い選択肢です。
コストも抑えつつ、十分に楽しめる。
それでいて家庭や仕事に支障が出ないレベルのバランス感を持っているのが魅力です。
ただし、「常に240Hzを安定させたい」と思うならRTX 5070やRX 9070を買うべきでしょう。
これらを選ぶことでこそ、高リフレッシュモニターの価値が輝く。
fpsがきちんと出ている時ほど、敵の小さな動きや位置を捉える能力は格段に上がり、反応速度にも直結するのです。
さらに忘れがちですが、今のGPUは単なる描画性能だけでは語れません。
低遅延機能の強化やAIによるフレーム生成技術など、以前では想像できなかった快適さを提供しています。
DLSS 4やFSR 4といった仕組みを実際に試すと、「なるほど、今どきの技術ってこういう意味があるのか」と思わされる。
重い場面でも滑らかさを維持しつつ、操作遅延のストレスが軽減される。
ただ一つ気をつけたいのは解像度です。
WQHDや4Kの映像美は確かに素晴らしい。
眺めている分には本当に感動するレベルです。
高解像度で得られるのはあくまで快適さや見映えであり、勝敗にはむしろ悪影響すら及ぼす。
配信者や観賞目的なら別でしょうが、勝ちを目指すならフルHD一択だと思うんです。
私なら迷わずそちらを選びます。
将来性を考えたGPU選びも大切です。
今満足できる構成でも、数年先には必ず物足りなさを感じる時期が来る。
数年前、周囲に「オーバースペックすぎる」と笑われた私の環境が、今ではむしろ標準的であることに驚かされるほどです。
この流れを考えると、多少余裕を見越して選んでおくほうが長い目で見て得をする。
結果として出費も時間も抑えられるのです。
どのGPUを選ぶべきかと問われれば答えはシンプルです。
144HzまでならRTX 5060 TiやRX 9060 XTで十分。
240Hzを維持したいならRTX 5070かRX 9070。
それ以上でも以下でもない。
ここさえ押さえておけば、余計な後悔はしなくて済む。
高リフレッシュモニターを買う時点で、ある程度の投資は避けて通れないんです。
GPUは基盤。
そこを削れば全体が崩れる。
思い出すんです。
私が最も後悔したのは、妥協してGPUを買った時でした。
結局、数年のうちに買い直す羽目になり、余計に出費がかさんだ。
それだけでなく、その間まともな環境で戦えず、機会損失も大きかった。
もし誰かにひとことだけ伝えられるなら「迷ったら一段上を買いなさい、未来の自分が助かるから」と声を大にして言いたいですね。
勝ちを目指す以上、環境作りで手を抜けば自分の努力の成果が正しく反映されません。
人生の限られた余暇を大事にしたいからこそ、私は納得できる投資をします。
自分の力を出し切るために、そして後悔しないために。
競技を意識するならCPUはどのクラスが安心か
以前、私はRyzen 5を使ってプレイしていましたが、大会と同じ設定にした途端にfpsが急落し、大事な場面で視点がカクつきました。
あの瞬間の、手の中からすり抜けていった勝機の悔しさは今でも強烈に残っています。
そう思うと、やはり選択の重みを痛感するのです。
「グラフィックボードさえ高性能なら問題ないだろう」と考えていた私でしたが、実際に足を引っ張ったのはCPUでした。
240Hzのモニターを本当に活かすには、CPUが安定して処理を回し続けないと意味がない。
fpsが急に落ちて一瞬リズムを崩すと、その隙を突かれて一気に流れを持っていかれる。
練習を積み重ねてきたのに、一瞬で努力が水の泡になってしまう。
その虚しさといったら……悔しすぎる。
もちろん、Core Ultra 5やRyzen 5でも軽く遊ぶだけなら全然問題はありません。
友達と気軽に試合するくらいなら十分です。
ただ、自分が本気で大会で戦いたいと思うなら話は別です。
私は当時、自分の実力不足だとばかり思って気にしていませんでした。
しかしPCを新調してみたら、実は環境そのものが足かせになっていたのだとわかったんです。
その気づきは衝撃で、少し悔しさすらありました。
もうひとつ、意外と見過ごされるのが冷却の問題です。
「スペックが十分なら安心」と思っていた私も、真夏にCPUクロックが落ちて安定しなくなる経験をしました。
あのときの焦りは忘れられません。
いくら性能が良くても、冷却が甘ければ本来の力は発揮できない。
大型の空冷ファンや水冷クーラーを導入してからは、静けさが増して集中できる時間が長くなりました。
静かに冷えるって、それだけで不思議と心も落ち着くんですよ。
Core Ultra 7に移行して初めてプレイしたときは、本当に世界が変わったと感じました。
fpsが常に240で安定し、その状態で撃ち合える。
試合中に余計な不安が消えて、ただ戦いに集中できる。
これは単なる数字ではなく、精神的な安定感につながるのだと実感しました。
安心感。
そして未来を考えると、さらに余裕が必要です。
Unreal Engine 5で作られる次世代ゲームは、確実に描画負荷が今の倍以上になります。
少々の先行投資で長く安定して使える方が、長期的にはコストも満足度も高まる。
40代になって改めて、そういう判断こそが「賢さ」だと思うのです。
最近はBTOショップの「Valorant推奨モデル」で、最初からCore Ultra 7やRyzen 7が標準搭載されているものをよく見ます。
本当に不要なパーツや性能は、すぐに市場競争で淘汰されますからね。
それでも残っているということは、必要だから残っているということ。
だからこそ、最適解といえるのです。
ではCore Ultra 9やRyzen 9にするべきか?よく聞かれる質問です。
結論から言えば、必要ありません。
もし4Kでの配信や同時並行作業をするなら検討すべきですが、Valorantに専念するのであれば完全にオーバースペック。
冷静に考えれば、そこまで求める必要がないと誰でもわかるはずです。
CPU選びというのは一見地味で目立たない部分です。
派手さはない。
ただ、ここで妥協すると勝敗に直結するのは間違いない。
だからこそ、私はCore Ultra 7やRyzen 7こそが「安心と実力を兼ね備えた最良ライン」だと考えています。
試合で勝ちたいなら、その土台を固めることが何より大事。
それがほんの僅かの差で勝敗を左右するのを、私は何度も見てきましたから。
CPUは単なる部品ではありません。
戦う環境の心臓そのものです。
そう思うからこそ私は断言します。
もし真剣にValorantで勝負したいなら、Core Ultra 7かRyzen 7を選ぶべきです。
これが勝てる環境を作る唯一の選択。
勝利への布石。
心から。
高リフレッシュレートモニターを組み合わせるときの注意点
部品同士の相性を間違えると、その投資の価値が半減してしまい、本当に悔しい思いをすることになります。
私にとって一番わかりやすかった教訓は、モニターのリフレッシュレートに関する失敗です。
240Hz以上のモデルを購入して「これで快適だ」と浮かれていたのに、肝心の接続ケーブルが古いままでした。
その結果、どうしても144Hz以上出力されず、おかしいなと数日間悩んだ末に原因がケーブルだったと気付いた瞬間、本当に情けなくなりました。
あのときは「せっかく高い買い物をしたのに、このざまだ」と夜中にひとりで苦笑しながら頭を抱えたのをよく覚えています。
さらに、盲点となりやすいのがCPUです。
ValorantのようなタイトルではGPUの馬力より、CPUの処理力がネックになる場面も多いのです。
私もRyzen 5クラスの環境で無理に240Hzを試してみたのですが、フレームレートが安定せず映像がガタつき、結局モニターの性能の一割も活かせませんでした。
そのとき本当に痛感したのは、「どんなに高性能なパーツを用意しても、全体の噛み合わせが悪ければ意味がない」という現実です。
冷静に言えば当たり前のことなのに、実際に体験してみると効くパンチのように心に刺さるんですよね。
購入前は「数値なんて多少違っても大差ない」とタカをくくっていました。
負けたときには「これ、ほんの0.1秒がすべてを分けたんだ」と悔しさで机を叩いたほどです。
逆に速い応答速度のモニターに替えた瞬間、敵の動きがくっきり見えて判断も明らかに早くできるようになり、「ああ、こういう差なのか」と感動すらしました。
まるで視界が一気に開けたようでした。
私も安価なケースで夏場を過ごそうとしたことがあり、その時には試合中に突然fpsが下がる現象に悩まされ、原因が熱だと気付くまで時間を浪費しました。
結局エアフロー重視のケースに変更したとき、ようやく安定性が得られたのは本当に嬉しかった瞬間です。
胸をなでおろしました。
モニターの設定も大切な要素です。
実際私もGPU側のドライバ設定が144Hzのままになっていたことにしばらく気付かず、「どうして出力されないんだ」と悩み続けて、最後に設定画面を開いたらあっさり解決した。
あのときは自分の凡ミスに思わず笑ってしまいましたが、小さな設定一つが大きな差につながるのだと学んだのです。
システム全体のバランスについてはさらに重視すべき点です。
最近のValorantはUnreal Engine 5ベースに移行し、映像処理の負荷が高くなっています。
グラフィックカードの性能だけでは十分な安定を得られず、メモリの速度やストレージの速さも鍵を握ります。
私自身、メモリ速度を甘く見ていたばかりに、大事なシーンで一瞬カクつき、そのワンプレーで試合を落としたことがあります。
心底悔しくて、「やはり環境をトータルで整えなくては意味がない」と叩きつけられるように思い知らされました。
結局のところ、モニターという単体の数値的なスペックだけに飛びつくのはあまりに危ういことです。
ケーブル、CPU、GPU、応答速度、冷却、メモリ、ストレージ。
すべてがしっかりと噛み合ったときに初めて、本物の240Hzや360Hzの世界が広がるのです。
だから私は新たな機材を導入する前に「この組み合わせは本当に意味を持つのか」と必ず自分に問いかけています。
正直に言えば、私も昔はただ数字の大きなものを追いかけさえすれば強くなれると信じていました。
しかし年齢を重ねて経験を積んでいくと、パソコンは一つ一つの部品がお互いに支え合い、バランスを取るからこそ最大限の結果を生み出すのだと理解しました。
この学びこそが、私にとっては一番大きな収穫だったのだと思います。
高リフレッシュレート環境を整える作業は見た目以上に奥深く、調整を繰り返す時間は長い道のりに感じられるかもしれません。
しかし、すべてがかみ合った瞬間に得られる快適さと安心感は、投資した金額以上の価値をもたらしてくれます。
だからこれからモニターを検討する人に、私は強く伝えたいのです。
数字や性能の高さだけではなく、全体の設計を意識して欲しい。
そうすれば最終的に勝率も安定し、ストレスのないゲーム体験につながります。
経験から言える、本当の実感です。
安心できる。
信頼できる。
そんな言葉こそ、最高の環境を示す何よりの証拠になるのだと、私は心から思います。
長く快適に使えるValorant用PCの選び方
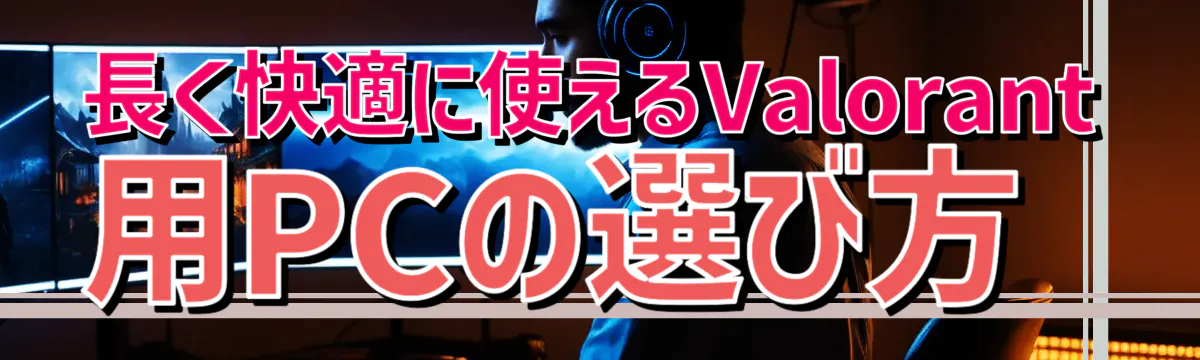
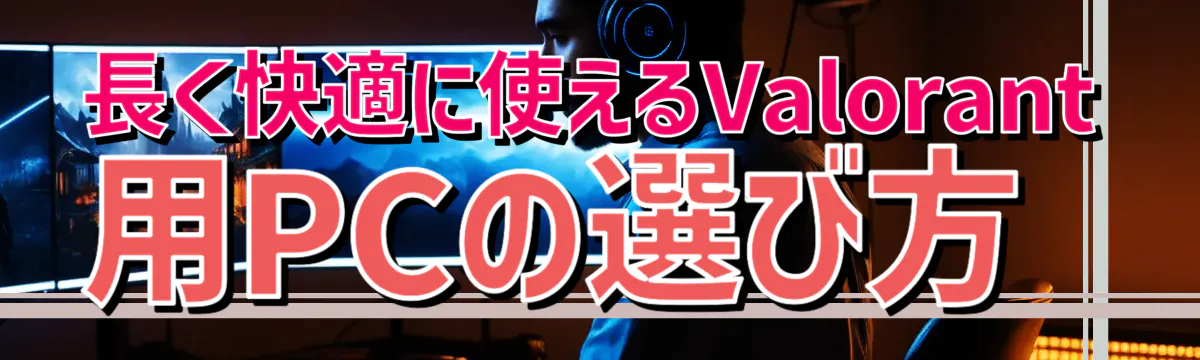
空冷と水冷、静音性と価格で考えたときのおすすめ
私自身、十年以上BTOパソコンを渡り歩いてきましたが、結局のところ大切なのは「自分の使い方に本当に合っているかどうか」だと思うのです。
ゲームを中心に遊ぶのか、仕事で動画編集を想定しているのか、それによって答えはまったく違います。
例えば空冷クーラーという選択肢。
仕組みが単純な分、壊れる要素が少ない。
だからこそ私のように何度もケースを開けて掃除してきた人間にとっては安心して使い続けられる魅力があります。
埃を取り除いてやれば、何年も信頼して稼働してくれる。
これは実体験として強く言えることです。
ゲームで言えば特にValorantのように極端な負荷がかからないタイトルでは、空冷クーラーでも十分すぎるほど快適に動きます。
「必要十分」という言葉がぴったりですね。
そしてコストの違いも見逃せない。
私が以前比較したときは、空冷構成と水冷構成でおよそ2万円ほどの差がありました。
その差額でSSDを追加したり、一つ上のGPUを手にした方がダイレクトに快適さが増すんです。
実際、フレームレートが数フレーム安定しただけでも、驚くほど体感は変わる。
プレイの満足度が違うんですよ。
だから「空冷で十分」という判断は、決して妥協ではなく現実的な最適解だと思うときがあるのです。
ただし水冷の強みを無視できるか。
水冷の魅力はやはり静音性と見た目、この二点に尽きます。
とりわけ夜中に仕事をしたりゲームをする私にとって、ファン音が控えめな環境は集中を妨げない大きなメリットです。
そして透明なケース越しに光る冷却ユニットを眺めていると、なんだかモチベーションが上がるんです。
正直言って自己満足。
でも日常的に使うものだからこそ、その自己満足は決して軽くはないと思うんですよ。
存在感があります。
もちろん理想だけでは終わりません。
水冷にはリスクがある。
私は過去にポンプが壊れ、一気にCPU温度が急上昇した経験があります。
あの時は本当にヒヤリとしました。
電源を落としたときには既に遅く、ソフトの温度表示が跳ね上がる瞬間を目にしたときの冷や汗は今でも忘れられません。
その一件以来、私は水冷を導入する際にはやや慎重になった。
改善されているとはいえ、不安はどこかに残るものです。
けれども用途によっては水冷の力強さは確実に役立ちます。
私は最近、動画編集を頼まれることが増えました。
長時間のレンダリングやゲームを同時に走らせるとき、360mmラジエーターを搭載した簡易水冷に変えてから体感は別物になりました。
熱だまりが格段に減り、夏場でも安定感を保てる。
以前は高負荷になると気持ち的に「PCに無理をさせている感じ」がしていましたが、そのしんどさから解放されたことは本当に大きな変化です。
値段が高くても後悔はありませんでした。
贅沢な安堵。
そうは言っても、多くの人にとってはやはり費用対効果のバランスが重要でしょう。
空冷の場合、優秀なモデルであれば1万円台後半からでも入手可能で、ほとんどのユーザーにとって困ることはありません。
逆に、「絶対に静音環境を手に入れたい」「ケース内を魅せるインテリアにしたい」というこだわりがあるなら水冷は意味を持つ。
結局は何を求めるかです。
ケースとの相性も大事な要素で、エアフローのよいケースなら空冷で十分だが、ガラスパネルの熱がこもりがちな構造なら水冷の方が向いている。
ここを見逃す人が多いんですよね。
最終的な私の答えはこうなります。
Valorantのように軽めのゲーム主体なら空冷で十分。
むしろ余った予算はGPUやSSDへ回した方が満足度が高いと断言できます。
反対に、長時間作業や重量級の処理、あるいは静かな環境を重視するなら水冷の導入を検討する価値があります。
冷静さと納得感。
これが残るかどうかで、日々の使い心地はまったく変わるのです。
私はそう信じています。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60YX


| 【ZEFT R60YX スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi A3-mATX-WD Black |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ Corsair製 水冷CPUクーラー NAUTILUS 360 RS ARGB Black |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56BR


| 【ZEFT Z56BR スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R64W


| 【ZEFT R64W スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R65W


| 【ZEFT R65W スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R52CM


プロゲーマー志望も夢じゃない、32GBメモリ搭載超高速ゲーミングPC!
新たなゲーム体験を!RTX 4060Tiが織り成すグラフィックの冒険に飛び込め
Fractalの魅力はただの見た目じゃない、Pop XL Air RGB TGが光るパフォーマンス!
Ryzen 7 7700の脅威の速度で、次世代ゲームをリードするマシン
| 【ZEFT R52CM スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
ガラスパネルケースとシンプルケースの違いと特徴
見た目の良さに心惹かれる瞬間は確かにありますが、40代になって毎日仕事終わりにPCに向かう時間が限られている身としては、やはり快適に使えるかどうかが全てです。
集中したいときにファンの大きな音や熱のこもりで注意が削がれてしまうと、一気に楽しさが色あせてしまうからです。
ガラスパネルケースは本当に魅力的です。
内部のパーツが美しく見え、ライティングが加わると所有欲をくすぐられます。
ところが一度、両面ガラス仕様を体験したときには、熱がこもって夏の夜にGPU温度が高止まりし、ファンの騒音に「これはしんどいな」とつぶやいてしまった経験があります。
せっかくの高い満足度が一気に冷めた瞬間でした。
インテリアとしては花丸。
でも、実用面では苦い思い出です。
一方で、装飾を削ぎ落としたシンプルケースには別の魅力があります。
派手さを求めなければ空気の流れがスムーズで、熱が自然に抜けていく安心感があります。
Valorantのような比較的軽いゲームを配信と同時に動かしても十分な余裕があり、音も静かで「え、こんなに違うのか」と驚かされました。
落ち着ける環境。
これに尽きます。
見栄よりも安定を重んじたい世代になった私には、この静けさがたまらなくありがたいのです。
その後何時間遊んでも気になるのはマウスやキーボードの操作音くらいで、熱に悩まされることはありませんでした。
この快適さは数値やスペックシートからは分からないもので、ただ実際に触れて長く使った人だけが深く実感できるものだと思います。
派手さはない。
だけど毎日使える確かさがある。
だからもしケース選びを相談されたら、私はいつも素直にこう伝えます。
見た目にこだわって心躍る時間を優先する人ならガラスパネルでいい。
ただ長時間安定して使いたいならシンプルケースがおすすめだと。
もちろんガラス仕様にも工夫の余地はあります。
高性能なファンや水冷を組み合わせれば熱の問題を抑えつつ、美しさも楽しめます。
要はケースそのものだけでなく、冷却システム全体をどう考えるかが本当の鍵です。
夜の時間は私にとって特別です。
仕事や家庭の責任から解き放たれ、ゲームで心を落ち着けたいのに、熱や騒音が邪魔をすると苛立ちを覚えます。
会議中に誰かがずっと机を叩き続けているような感覚。
耐えられません。
だからこそ、私は声を大にして言います。
基準は冷却性と快適性。
この二つだけでいい。
けれど数か月後には吐き出すため息ばかりが増え、集中できない自分に嫌気が差しました。
そこから学んだことは一つ。
結局のところ暮らしに寄り添ってくれるのは快適さだということです。
逆にシンプルケースを導入したときは、起動してからゲームに没頭するまで何ひとつ気にせず自然に楽しめて、「ああ、これだよ」と腑に落ちました。
実はこの「当たり前の快適さ」を作り出すのがいちばん難しいのです。
仲間に相談されれば私は迷わずこう答えます。
派手なライティングで胸を弾ませたいならガラス。
ただ、静かに集中して楽しみたいならシンプル。
どちらにも正解はあります。
快適な環境を守るのは冷却性で、それを軽視するとどんなに美しい装飾も色あせます。
どちらを選んでも間違いではないと思います。
ただ大切なのは「最後まで後悔しない選択」をすること。
勝ち負けを左右するのは外観の華やかさではなく、どれほど静かで冷えているかという一点。
最終的に残るのは、快適な時間を守ってくれるかどうか。
それだけです。
以上が私の実体験を踏まえたケース選びの考え方です。
表面的な派手さに惑わされず、自分が毎日どう使いたいか、どんな環境で過ごしたいかを自問することこそが、本当に満足できる一台を手に入れる近道なのだと思います。
電源ユニットは750Wと850W、どちらを選ぶのが現実的?
PCを組むとき、つい目に入りやすいのはCPUやGPUの性能ですが、実は土台を支える電源ユニットの選択こそが長く使ううえで大きな差を生みます。
私はこれまで何度もパーツを入れ替えてきましたが、その経験から間違いなく言えるのは、電源を妥協すると必ず後悔する場面が訪れるということです。
特に750Wか850Wか、この100Wの差をどう考えるかで、快適さと安心感に大きな違いが出てきます。
私は自信を持って850Wを選ぶことをおすすめします。
初期コストは少し高くても、長期的に考えればその差は十分に回収できるからです。
以前の私は、正直に言うと「750Wもあれば十分だろう」と思っていました。
ちょっとだけでも予算を浮かせたい、そんな気持ちも強かったんです。
しかし新しいGPUに替えてゲームを始めると、ピーク時に電力が跳ねて画面がガタつく現象に何度か遭遇しました。
あの瞬間の不安といったら…。
せっかく楽しみたくて組んだPCなのに、動作が不安定になって冷や汗をかいたのを今でも覚えています。
だからこそ今では、電源部分だけは安易に妥協しないように心掛けています。
最近のGPUは侮れません。
仕様書にある消費電力だけを見て「問題なさそう」と思っても、実ゲームプレイでは一気に電力を食うことが多々あります。
RTXシリーズや最新のRadeonは特に顕著で、余裕のない電源では一瞬の高負荷でブラックアウトやクラッシュを引き起こす可能性があるのです。
遊びたいときに限って落ちるなんて、これほどストレスなことはありません。
だから私は電源を選ぶとき、数字上の理屈よりも「余裕」を最優先しています。
安心できる余裕です。
それに容量の大小だけでなく、効率グレードも無視できません。
効率の良いモデルを選べば、発熱も少なく電気代だって抑えられますし、深夜にゲームをしているときにファンの音が気になることも減ります。
私は以前、静かな夜にFPSをやっていて、ファンの風切り音で集中を削がれたことがありました。
その体験以来、多少の差額であっても効率の高い電源を買うようにしています。
その積み重ねが最終的には生活全体の快適さにつながるからです。
850Wの魅力は安定性だけではありません。
私は仕事の息抜きにゲームをしながら配信をすることがあります。
そのときにアプリを同時にいくつか立ち上げるのですが、850Wなら動作が途切れる心配はほとんどありません。
しかも負荷が下がる分、発熱も抑えられ、ファンの音も穏やかに保てます。
集中力を奪い、楽しささえ削いでしまうものです。
静かに安定して動くPCが、どれだけ心地よいか。
これは実際に体験しないと分からないと思います。
確かに価格だけを見れば750Wの方が財布に優しいのは事実です。
けれどGPUの更新サイクルを考えれば、次世代のカードが出るたびに少しずつ消費電力が増えていく現実があります。
買い替えを見送るたびに「電源、大丈夫かな」と不安に思う必要がないのです。
そんな気持ちの負担から解放されるのは、実はすごく大きなメリットなんですよ。
発熱の観点でも差が出ます。
750Wで常にフル稼働状態だと、どうしても熱を持ちやすくなります。
するとファンの回転数が上がり、音がどんどん耳につく。
肝心のゲームの場面で集中できなくなるのは、もったいなさすぎます。
それに対して850Wなら余裕を持って働くので、結果的に低温かつ静音。
少しの違いの積み重ねが、想像以上の快適さを生んでくれるんです。
私はよくフルHDからWQHD解像度でプレイしますし、配信も並行してやります。
そんな環境では750Wでは心細さを覚える場面が確実に出てきました。
ただ電源を850Wに変えてからは、その不安が消え去り、心からゲームに没頭できるようになっています。
この「気がかりがない」という状態が思った以上に大切で、画質やフレームレート以上に体験を豊かにすると改めて感じています。
もちろん、全員にハイエンド環境が必要なわけではありません。
ただ、それはあくまで今の用途に限った話です。
本当に悔しい瞬間です。
確かに初期投資は少し増えます。
しかしその差額が長期的には安心と拡張性への投資になるのだから、決して高い買い物ではありません。
電源は目立たない存在ですが、PC全体を支える心臓部のようなもの。
心臓が弱ければ日常は揺らぐ。
私はそう実感してきました。
だから今は迷うことなく850Wを選んでいます。
私は心からそう思っています。
Valorant用ゲーミングPCを買う前によくある疑問
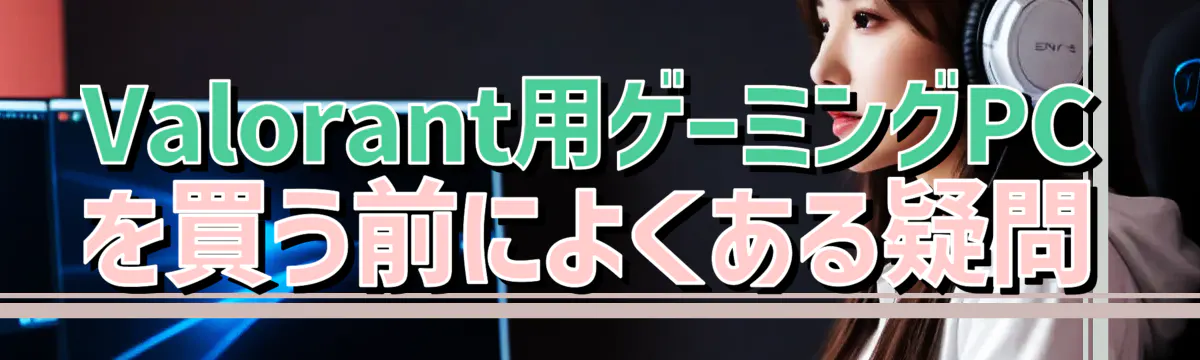
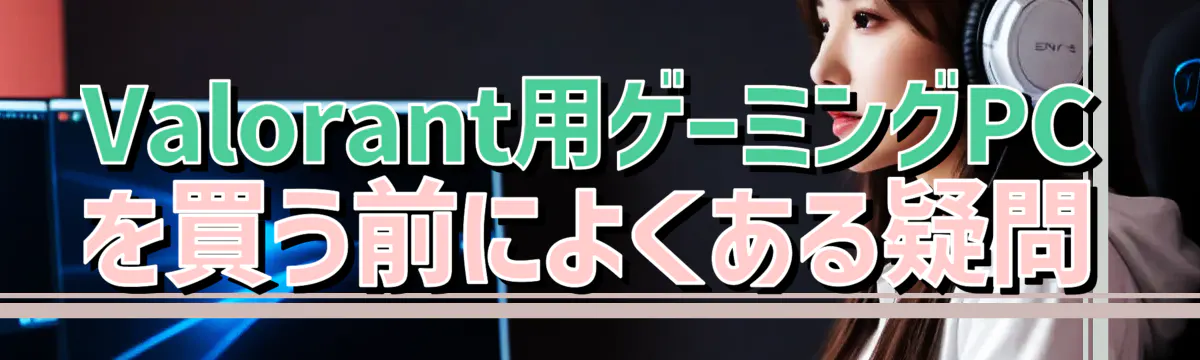
Q. 15万円の予算でしっかり遊べるPCは買える?
15万円の予算でも、きちんと考えて組めばゲーミングPCとして十分な性能を確保できます。
大切なのは「どのゲームをプレイするのか、どんな画面環境で遊ぶのか」を最初にはっきりさせてからパーツ選びに取りかかることだと私は思います。
予算が潤沢にあるなら考え方も変わりますが、限られた枠の中で最大限の満足度を得るには、無駄に背伸びせず、自分に必要な性能を冷静に見極めることが一番です。
私は以前、実際に15万円ほどのBTOモデルを購入しました。
そのときは正直、半信半疑でしたね。
「この金額で本当に遊べるのか」と。
でも、実際に手元に届いてゲームをプレイした瞬間、不安は吹き飛びました。
Valorantのような軽めのタイトルならフルHDで200fps前後は安定し、映像の滑らかさに思わず唸ったものです。
拍子抜けするほど快適で、「これでもう十分じゃないか」と独りごとが口をついて出ました。
あの感覚は今でも鮮明に覚えています。
選んだ構成は、Core Ultra 5クラスのCPUとRTX 5060 Ti。
最上位というわけではないですが、いわゆる実用本位の組み合わせです。
無駄に高額なモデルに走らず、ちょうどいいところを選んだ満足感。
20万円や25万円を使ったからと言って、常に幸福度が比例するわけじゃないんですよね。
肩の力が抜けて、結果的に長く遊べる。
そんな買い物になりました。
ただし、予算の配分で失敗しやすいのがメモリとストレージです。
ここを削ってしまったら後々必ず後悔します。
ゲーム本体は軽くても、録画や同時進行する他のタイトルで容量はあっという間に消えますから。
私は一度、500GB SSDで済ませたことがありますが、数ヶ月で埋まってしまい、大慌てで外付けを買い足す羽目になったんです。
だから今の私なら間違いなく最初から16GBメモリと1TB SSDを選びます。
後から足すより、最初から整えておいた方が気持ちが楽です。
心からそう思います。
冷却や電源も軽視してはいけません。
私は昔、見た目を重視してガラスパネルのケースを買ってしまい、真夏に熱で悩まされました。
ゲーム中にフレームが乱れ、パーツを活かせず悔しい思いをしたんです。
あの経験は強く心に残っています。
GPUに関しては、RTX 5060 TiやRadeon RX 9060 XTがこの価格帯における最適解だと感じます。
もちろん、さらに上位の5070あたりに惹かれる気持ちもわかります。
予算の範囲を守る潔さも必要です。
背伸びをしないからこそ、長持ちする安心感があるんだと思います。
CPUならIntelのCore Ultra 5 235か、AMDのRyzen 5 9600。
この辺りがちょうど良い選択肢です。
性能というものは常に上がっていくので「もっと良いものを選ばないと不安になる」気持ちは尽きませんが、必要十分という言葉の意味を理解できるのは大人になってからなのかもしれません。
仕事柄シングル性能を重視する私ですが、ゲーム中心ならバランスの良いRyzen 5 9600を選ぶのも十分納得できます。
上を見ればきりがない。
ほんとにその通りです。
15万円で手に入るPCは、フルHDに特化した競技環境向けと考えればわかりやすいです。
ここで「割り切り」が効いてきます。
解像度や用途をはっきり決めて、それに見合った構成を選ぶ方が、満足度はずっと高くなる。
私は何度もそう実感してきました。
eスポーツ大会で導入されるPC構成を見ても、ミドルレンジの構成で固めている例が圧倒的に多い。
結局はそこに安定性があるんですよね。
「高価格=ベスト」ではないと知ると、気持ちがスッと楽になります。
安心するんです。
私なりに整理すると、CPUはCore Ultra 5 235かRyzen 5 9600、GPUはRTX 5060 TiかRadeon RX 9060 XT、メモリは16GB、ストレージは1TB SSD、冷却は信頼できる空冷、ケースはエアフローを重視。
それで15万円に収まる。
そしてValorantクラスのゲームであれば、何も不安は感じません。
欲を出さなければ、これで十分。
性能表の数字だけを見比べて判断する人は多いでしょう。
しかし実際に必要なのは、自分自身が納得してゲームに熱中できるかどうか。
私はその答えを、自分の15万円PCで確かめました。
そして今もなお、不満なく遊べています。
それで。
Q. 長期的に考えるならメモリは32GBがいい?
真っ先に触れておきたいのは、Valorantをプレイするために必要なメモリ容量のことです。
実際、私が友人から依頼を受けて組んだパソコンでも16GBのDDR5を搭載しており、240Hzのモニターで実に軽快にプレイできていました。
ゲーム中に「あれ、動作が重いな」と思う瞬間は一度としてありませんでした。
とはいえ、正直に申し上げると、それは今この瞬間の話にすぎません。
将来を見据えた場合、32GBを選んでおいた方が明らかに安心ですし、余裕をもって構えていられるのです。
ゲームの世界は常に進化し続けています。
新しいタイトルがリリースされるたびに、必要とされるスペックは一段上がるのが常識です。
特に近年注目されているUnreal Engine 5の登場以降、GPUやCPUだけでなくメモリにまで相当な負荷がかかるケースが増え、これまでの基準では物足りなくなる日も遠くありません。
未来のアップデートや高解像度配信を視野に入れるなら、32GBにしておいた方がいい。
ここで一歩踏み込むのか、それとも様子を見るのか。
その選択によって数年先の快適さは大きく変わりますから。
私が日常でゲーミングPCを使うとき、遊ぶだけでは終わりません。
ゲームをしながら配信を同時に立ち上げ、裏でブラウザを複数開いて調べものをし、さらに動画編集ソフトまで起動させる。
気づけばフル稼働です。
その状況で16GBだと限界が早く訪れ、アプリが突然落ちたり画面がカクついたりして、正直苛立ちを覚えました。
最終的に32GBに増設したことでようやく不安から解放され、作業や趣味に集中できるようになりました。
こうして実際に体感した差は小さなようでいて、日々の積み重ねの中でかけがえのない安心感を与えてくれます。
最近はDDR5メモリの価格もぐっと落ち着いてきました。
以前は32GBというと「やや贅沢」という印象がありましたが、今はむしろ現実的かつ堅実な選択肢に見えます。
BTOパソコンで16GBから32GBにカスタマイズする場合も価格差は1万円前後。
これで性能強化と将来の安心を手に入れられるのなら、むしろ安い投資だと私は感じています。
例えるなら、スマホのストレージを最初に選ぶときの話に近いです。
購入時には「128GBあれば十分」と思い込んでいたのに、写真やアプリがどんどん増えて、結局あっという間に不足してしまう。
結局はクラウドや外部ストレージに頼る羽目になる。
こうした経験をした人は多いはずです。
同じようにPCでも、最初に16GBを選んでしまうと、後から不自由さに気づき、余計な我慢や買い替えを迫られる。
だからこそ、余裕を持った32GBという選択は後から自分を助けるのです。
思い返せば、私が配信をつけながらValorantをプレイしていた時もそうでした。
16GBの環境で快調に始まったはずのゲームが、配信負荷と相まって急にカクつき始める。
滑らかだった画面が突如としてぎこちなくなり、視聴者から「止まってますよ」と指摘される度にイライラが募りました。
あの瞬間のストレスは鮮明に覚えています。
あんな経験をした以上、「もう16GBには戻れない」と強く実感したのは当然です。
もっと多ければさらに万全だろう、そう考える方もいるかもしれません。
しかし64GBを超えるとコストは一気に跳ね上がりますし、Valorantのような軽量級のタイトルにそこまでの容量は必要ありません。
性能と価格のバランスを考えれば、32GBが極めて現実的で妥当な答えになります。
私は常に費用対効果を大事にしていますから、その判断は自然に受け入れられるものでした。
CPUやストレージ強化も魅力的ですが、後から交換が効くパーツです。
たとえValorant専用を想定していたとしても、後から配信や動画編集といった幅広い用途に手を広げると、必ず不足を感じる瞬間が来る。
だから32GBへの投資は、スペックのためというより心の余裕を買う行為に近いと私は思っています。
迷った時は、数年後の自分がどう感じているかを想像してみると答えが出ます。
結局のところ、後悔しないのは余裕を残した選択肢です。
私は断言しますが、多くの人にとって32GBという選択は長期的に正解です。
そして最後にもう一度だけ伝えておきたいのです。
後悔しないように、納得できる構成を選んでください。
安心できる未来のために。
落ち着いた選択を。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55HI


| 【ZEFT Z55HI スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285 24コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56AD


| 【ZEFT Z56AD スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CO


| 【ZEFT R60CO スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DY


| 【ZEFT Z55DY スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
Q. BTOショップで選ぶときに気をつける点は?
BTOショップでPCを選ぶときに私が一番大切にしているのは、単に性能や価格を比較するだけではなく、自分がどんな時間をそのPCと過ごしたいのかを具体的にイメージすることだと思います。
実際のところ、ゲームを快適に遊びたいのか、仕事にも兼用したいのか、あるいは長く愛着を持って使いたいのか。
その答えが決まれば、おのずと正解が見えてきます。
特に私の場合はValorantを念頭に置いていることが多いため、グラフィックボードとCPUの組み合わせをどうするかが最大の決め手になります。
1080p環境で240fpsを安定させたいならそれ相応の構成は必要で、ここを妥協すると一気に快適さが失われます。
私は以前に少しスペックを落としてしまった結果、半年も経たないうちに買い替えを余儀なくされたことがあります。
その時の後悔は今も忘れられませんね。
各BTOショップにはそれぞれの良さと特色があります。
それを知ることが、自分に合ったPCを選ぶための大きな助けになるのです。
例えばDellです。
ビジネスPCでの強みをそのままゲーミングPCにも展開しており、特にサポート体制は群を抜いています。
私も仕事でDellを使ったことがあり、急なトラブルで困った時に素早く対応してくれた安心感は今でも印象に残っています。
大げさかもしれませんが、あの瞬間は「助かった…」と心底思いました。
初めてのゲーミングPCを買う方にとって、この安心感はきっと大きな価値になるはずです。
ただしパーツの細かいカスタマイズができないという不便さはありますが、総合的に完成度の高いPCを欲しいという人には間違いなく選択肢になります。
一方で、ドスパラは本当にスピードが強みです。
注文から到着までの早さは他社と比べても頭ひとつ抜けています。
待たされない。
これこそ最大の魅力だと私は感じます。
私の知人は金曜日の夜にゲーミングPCを注文したのですが、なんと月曜日には自宅に届いたそうです。
その話を聞いて思わず「えっ、そんなに早いの?」と声に出してしまいました。
急にゲーム仲間と集まることになったとか、仕事の合間にすぐ使いたいといった状況では、このスピードがものを言います。
この体験はやっぱり心を踊らせるものです。
そしてパソコンショップSEVEN。
ここは昔からある安心感と同時に、近年は攻めの姿勢も感じられるショップです。
特に私が好きなのは豊富なコラボモデルでしょうか。
NZXTやLian Liといったケースメーカーとの組み合わせは、外観や質感までしっかりと楽しみたい人にとって嬉しいポイントです。
私は部屋にPCを置いたときの雰囲気も大事にしたいタイプなので、この柔軟さには好感を持っています。
見た目も性能も、長く愛用できること。
その両方を叶えてくれるのがSEVENの良さだと思います。
組み立ての細かさやパーツの品質もしっかりしているので、購入者の満足度が高いのも納得の結果です。
最終的にショップを選ぶ時の軸は、保証を取るのか、スピードを取るのか、品質を取るのか。
この三つのうちどれを優先するかで結論は変わります。
Dellは頼れるサポートで安心を担保してくれる。
ドスパラはスピード感で期待に応える。
そしてSEVENは高品質という武器で「長く使える安心」を提供する。
それぞれに明確な特徴があるので、迷いそうで実は選びやすいとも言えます。
私は今40代になり、若い頃のように性能の数字だけを追いかけることはなくなりました。
むしろ長期的に安心して使えるかどうかが最も重要だと考えるようになっています。
もし今Valorant用PCを買うなら、私は状況に応じて選び分けます。
例えば急遽「来週から友人と本格的に遊びたい」と思ったなら、スピード重視でドスパラを選ぶでしょう。
でもじっくり長期間腰を据えて使うメインマシンとしてなら、SEVENを選ぶと思います。
そして仕事と兼用しつつ安心のサポートを求めるなら、Dellに頼りたい。
選択が変わるのは、私の生活や時間の使い方が変わるからです。
だからこそ正解は一つではありませんね。
最後に伝えたいのは、どのショップが良い悪いではなく、自分がこれからPCに何を求めたいのかを最初に考えることです。
結局その答えがショップ選びの指針になるのです。
Q. SSDはGen4かGen5、どちらを選ぶのが良い?
Valorantを快適に遊ぶためのSSDを選ぶなら、私はGen4が最適だと思っています。
なぜなら、ゲームを実際にプレイしていてもGen5の速さがほとんど実感できないからです。
ベンチマーク上で誇らしげに並ぶ桁違いの転送速度の数値は、確かに心をくすぐります。
新しいもの好きの人たちはきっとその数字だけで引き寄せられることでしょう。
ただし、実際のゲーム体験にどれだけ意味があるかと言えば、答えは「ほとんどない」なのです。
ロード時間はGen4でも体感的にはほぼ瞬時といえるレベルで、私はこれまで何百時間もプレイしてきましたが、起動待ちに苛立った記憶が一度もありません。
一方でGen5の課題ははっきりしています。
まず、発熱問題が深刻です。
大型のヒートシンクが存在感を主張しすぎて、パーツの配置一つ変えざるを得なくなる。
小型ケースではなおさら悩ましい。
しかもファン付きの冷却機構を備えたモデルなんて、静音環境を大事にしている私にとっては「いやいや、これは困るぞ」と思わせる存在です。
SSDを追加したせいで逆にPC全体の騒音や温度が上がるなんて本末転倒ですよね。
性能差を感じられないのに高価な投資を強いられる。
実際に私はGen5を仕事用マシンで導入したことがありました。
動画編集で巨大なデータを取り扱う際、その性能は驚異的でした。
例えば数十ギガの動画データ移動が圧倒的に短時間で終わり、作業効率が劇的に改善されました。
そのときは「なるほど、これが次世代の力か」と素直に感動したものです。
しかしゲーム用途ではどうかというと、何も変わらない。
むしろ冷却ファンを増設するなど余分な調整に時間も手間も取られました。
そこで私が得た答えは「これは仕事には最適だが、ゲームには不要」というシンプルな結論でした。
ゲームのために余計なストレスまで増えるなんて、笑えない話です。
だからこそ、Valorantを遊ぶ前提ならGen4 NVMe SSDで十分。
1TBや2TBの容量を搭載していればアップデートも困らないし、他のゲームを複数インストールしても余裕があります。
何より「これでまったく困っていない」という手応えを持てるのが大きいんです。
気兼ねなく安心して使える。
未来を見据えたときにGen5が無駄な選択肢かというと、決してそうとは思っていません。
これからのゲームがより高速なストレージを前提とする時代がやってくれば、Gen5が強力な武器になるでしょう。
AI処理や映像技術がスタンダードになってくれば、それはもう必要不可欠な存在になっているに違いありません。
私はPC業界の動きを追いながら、何度も「やがてこれは常識になるな」と感じた瞬間があります。
ただ、重要なのは「今どうするか」なんですよ。
現時点では、ゲーム用途でSSDを選ぶならGen4が正解です。
無理に高価なGen5を選んでも、性能を存分に活かす場面は訪れませんし、結局は価格に見合わないまま数年後には型落ちになるリスクが高いです。
それならば必要になったときに導入すればいい。
その頃には今より安定した製品ラインナップになっていることでしょう。
だからこそ私は「今はGen4」とはっきり言い切ります。
それよりも投資すべきは別の部分です。
例えば同じ予算をグラフィックボードに回せば明らかにフレームレートの向上を実感できますし、CPUを一段階良いものにした方が長く快適に遊べる環境を作れます。
ゲーム体験を左右するのはSSDのベンチマーク値よりも画面の滑らかさや安定性だと、私は身をもって感じています。
時には数字の良さよりも、体感の良さがすべてなのです。
プレイ中のストレスを減らすこと。
これが一番の目的です。
Valorantを遊ぶなら、まずGen4で問題なし。
プレイヤーが本当に欲しいのは「安定して楽しめる環境」なんだと思います。
毎日PCを立ち上げるたびに「ああ、今日も快適だ」と感じられる。
それが最高の価値だと思うんです。
最後に強調しておきます。
SSD選びで迷っているのなら、私は自信を持ってGen4をおすすめします。
無駄のない賢い選択ですし、これで安心してゲームに集中できます。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
Q. ケースを選ぶとき冷却以外で注目すべきポイントは?
冷却は確かに重要で、特にValorantのような負荷がかかるゲームでは欠かせない基盤のような存在です。
しかしそれだけで決めてしまうと、後々「どうしてこんな扱いにくいケースを選んだんだ」と後悔する瞬間がやってきます。
私はかつて性能重視で選んだものの、メンテナンス性や拡張性を軽視した結果、不便さを引きずってしまった経験があるので、今は強くそう思います。
拡張性というのは、未来への余白なんです。
今は十分でも、数年後には必ず「もうちょっと」を求める日がやってきます。
このショックは想像以上でした。
実際私は小さめのケースを選んでしまったことがあり、購入した最新パーツを机の横で眠らせる羽目になりました。
二度と味わいたくありません。
デザインも決して軽んじるものではありません。
毎日机に置いて使うからこそ、見た目が心の状態にまで響いてきます。
私はガラスパネルや木目調デザインを見かけたときに、思わず「これ、いいな」と声が出ました。
道具でありながらインテリアの一部にもなる。
美しいものに囲まれていると気持ちが前向きになるんです。
自己満足と言われても構いません。
私にとっては仕事や趣味に向き合う集中力を高めてくれる、大切な要素なんです。
見た目の力。
昔、裏配線機能のない古い設計のケースを選んでしまい、配線がゴチャゴチャのまま数年使ったことがあります。
作業のたびに「何でこんなのを選んだんだ」と自分に呟いていました。
見えない部分の利便性って、日常の快適さをこんなに左右するのか、とそのとき痛感しました。
裏配線やメンテナンス性は、軽視すると長い時間ずっと後悔を背負う要因になるんです。
静音性も忘れてはいけません。
私は静音ケースを初めて導入したとき、本当に驚きました。
静かすぎて逆に不安になるほどで、「あ、これはもう戻れない」と声が出ました。
雑音がなくなるだけで、通話や配信もぐっと快適になるし、作業もゲームも全然違う。
静けさのありがたみって、実際に味わってみてようやく理解できました。
使い勝手の点で案外重要なのがインターフェースです。
USBポートやオーディオ端子の数や配置が合わないと、不便で仕方ないんです。
あるとき私は配信をしようとして周辺機器を接続しまくり、結局端子が足りずに後悔しました。
前面に端子があったら一瞬で解決するのに、そうじゃないだけで「もう嫌だ」と毎回つぶやいていた自分を思い出します。
小さな要素。
でも快適さの差は大きい。
耐久性も見逃せません。
見た目が立派でも剛性が弱いケースは、本当にすぐ歪むんです。
内部の基板に悪影響を及ぼすことすらあります。
その点、しっかりした剛性感のあるケースは、ずっしりとした安心を与えてくれます。
私は実際、パネルがよじれて内部パーツが壊されたケースを目の当たりにしたことがあり、背筋が寒くなりました。
堅牢さそのものが信頼性に直結します。
まとめれば、Valorant用にPCケースを選ぶなら、冷却だけでなく拡張性やデザイン性、メンテナンス性、静音性、インターフェース、耐久性、この六つを総合的に見ることが肝心だと私は思います。
どれか一つを軽視すれば、必ず使い始めてから悩みが生まれます。
逆に一つ一つ丁寧に確かめれば、長く快適に付き合える相棒が手に入る。
大げさではなく、本当にそうなんです。
私はこれまで数々の失敗から学んできました。
だから今はPCケースを選ぶことそのものを一種の楽しみだと思っています。
「ただの箱」なんかではない。
私にとっては一緒に戦い、一緒に過ごす存在。
それがPCケースです。